
教えてくれた人
大久保雄(おおくぼ・ゆう)/埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科准教授。リハビリテーション科学やスポーツ科学分野での研究を行う。
1.背骨のS字カーブが整って姿勢がよくなる。
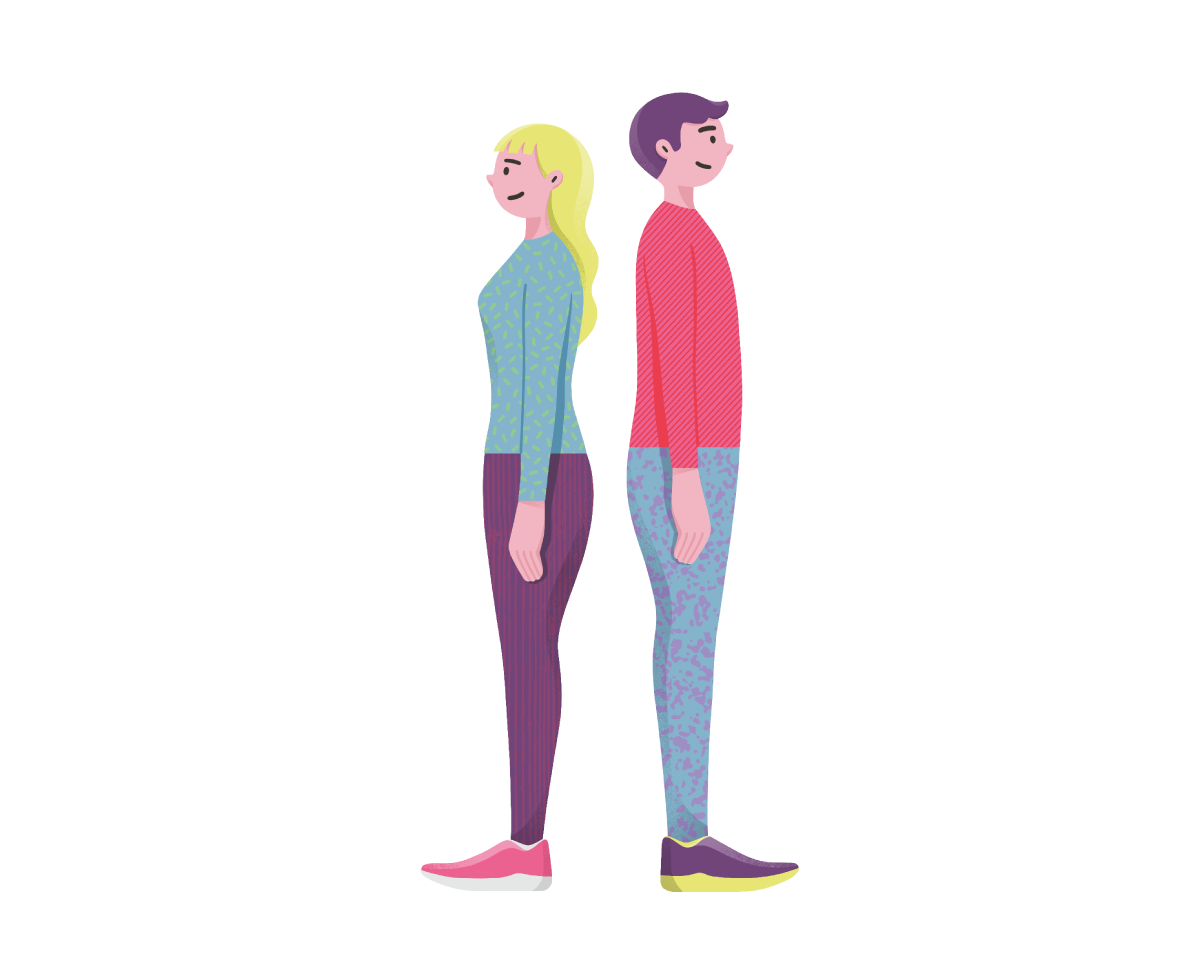
耳、肩、腰、膝、くるぶしを結んだ線が一直線である美姿勢を保てるのは腸腰筋のおかげ。
鳥とか恐竜とか2本の足で立つ生物はヒト以外にもいるけれど、ビシッと上体をまっすぐ保って立ったり歩いたりできる生き物はヒトしかいない。
その理由は背骨が芸術的ともいえる生理的カーブを描いているから。首の部分の頸椎は前に向かってカーブし、胸椎は逆に後ろに向かって彎曲し、その下にある腰椎は再び前彎している。このS字カーブの絶妙なバランスが重い頭の負荷を分散し、カラダの真上にキープし続けられる理由。
で、腰椎の前彎にひと役買っているのが腸腰筋の一部である大腰筋後部線維。この筋肉がきっちり収縮できるから背骨のS字カーブが保たれ、美しい姿勢を維持できるというわけ。
2.歩幅が広がり、躓きにくくなる。
歩く能力=移動機能が低下するロコモティブシンドロームのリスクを洗い出すためのテストのひとつに、「2ステップテスト」と呼ばれるものがある。
スタートラインからできるだけ大股で2歩歩いて合計の歩幅を測る。この数値を身長で割り、ロコモ度を判定するというテストだ。数値が1.3未満だとロコモの入り口に立っていると判定される。
腸腰筋が機能していれば、股関節を曲げて一旦引きつけることで大きな一歩が踏み出せる。この歩幅の感覚を日常にも活かせれば、ロコモのリスクを遠ざけることが可能。まだ先の話? いや、普段の歩行で躓くことがあるならば他人事ではない。腸腰筋ケアで歩幅の拡大に努めるべし。
3.頭の位置が修正されて肩こりが改善する。

慢性肩こりの原因のひとつは頭の位置が前に出すぎていること。腸腰筋ケアで改善を。
ひと口に猫背と言っても、そのタイプはさまざま。たとえば、腰椎の前彎が甘くなり、背骨のS字カーブが失われ、緩やかに後ろに彎曲している姿勢。これがいわゆる「フラットバック」という猫背姿勢。あるいは骨盤が後ろに倒れ、バランスを保とうとして胸椎の前彎がキツくなり首が前に出る「スウェイバック」。これもまた猫背姿勢のひとつだ。
どちらにしろ頭の位置が通常より前に位置し、頭の重みがもろに肩や首の筋肉にかかる。こうした姿勢が習慣になれば肩や首の筋肉の血行が滞り、老廃物が除去できず、肩こり・首こりを引き起こす。何をしても凝りが解消しないなら、硬くなったり弱くなっている腸腰筋ケアを試してみる価値あり。
4.骨盤のポジションが改まり腰痛から解放される。
電車で座っている人の姿勢をチラ見してみてほしい。背もたれと座面が直角に交わる部分にお尻をくっつけて座っている人は驚くほど少ない。どういうことかというと、お尻が座面の前面にズレていて、おそらくおヘソが天井を向いている。これが典型的な骨盤後傾の姿勢。おや、もしやあなたも?
このまま立って歩くとしたら確実に負荷を逃がす腰椎の前彎が失われた状態になる。その結果、上半身の負荷がもろに腰椎にかかり、腰痛が生じることに。
繰り返すが大腰筋の後部線維は収縮し、腰椎を前に押し出す働きをする。このとき骨盤は若干前傾した状態で腰椎への負担は最低限。本来の大腰筋の機能を取り戻せば、腰痛ともサヨナラできるはず。
5.自律神経のバランスが整って疲れにくくなる。
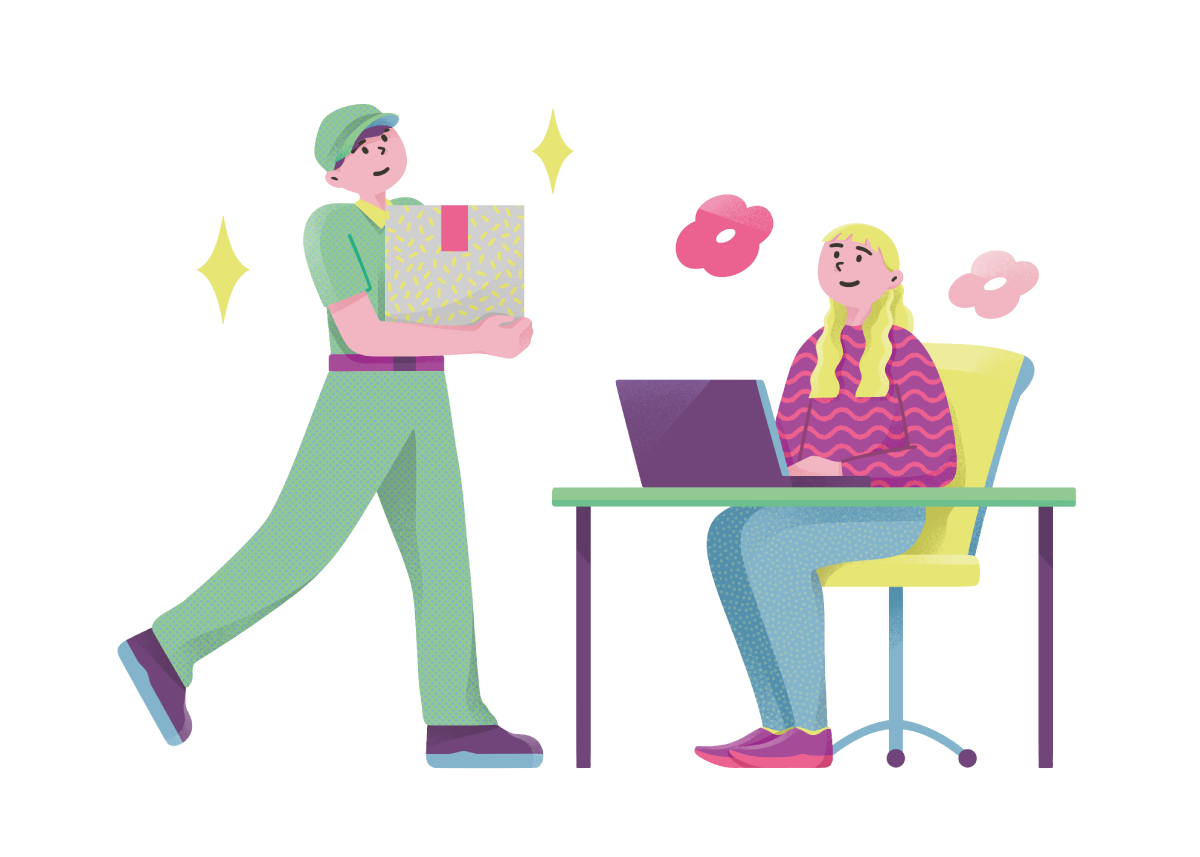
自律神経は睡眠や内臓機能、ホルモン分泌にも関与する。整えることで疲れにくくなる。
病名が付かないカラダの不調が続くとき、原因の候補として「自律神経の乱れ」が挙げられることが珍しくなくなった時代。
ご存じの通り、自律神経とは日中のアクティブな活動で機能する交感神経と、夕方以降の休息時に主に働く副交感神経の総称。ふたつの神経がバランスよく活性化することで健やかな身体活動を維持できる。
自律神経は背骨に沿う形で走っていて、交感神経は胸椎と腰椎周辺から、副交感神経は脳幹と仙椎という骨盤周辺から全身の器官に神経を延ばして情報を伝える。なので、正しい姿勢を保つことが自律神経の健全な働きに関わるという説もある。腸腰筋ケアによる姿勢改善が自律神経機能を助ける可能性も十分考えられるのだ。
6.お腹まわりのだぶつきがなくなりスッキリする。

お腹まわりの引き締めには最奥にある腸腰筋を働かせることが近道かも。
一般的に腸腰筋を手で触って確かめることができないのは、体幹の深層にある筋肉だから。カラダの前面で言うと、腸腰筋の上には腹横筋というハラマキのようなインナーマッスルがあり、さらにその上を腹斜筋という脇腹の筋肉が覆い、最も外側に腹直筋、いわゆるシックスパックと呼ばれるアウターの腹筋がある。
股関節前面を経由する腸腰筋は股関節を曲げるという働きだけではなく、下腹部を覆うこれらの腹筋群と協調して働くと考えられている。姿勢の安定や股関節を動かすだけでなく、体幹筋としての一面もあるわけだ。
そう考えれば、腸腰筋を鍛えることでウェストまわりの引き締めや下腹部のシルエットがスッキリする可能性は大。
7.階段を軽快に上れるようになる。
階段を1段ずつ上っている分には腸腰筋はほとんど稼働しない。膝を曲げてトボトボ上っている場合はなおさらのこと。階段の1段抜かしで腸腰筋のブーストがかかるのは、股関節の屈曲レベルが高まるだけでなく、後ろ脚の股関節が十分に伸展されるからだ。筋肉は最大伸展と最大屈曲のセットでその機能を盛大に発揮する。
ならば、階段を1段ずつ上るときもできるだけ股関節の伸展と屈曲を意識しよう。腸腰筋が少しでも稼働するようになれば、大腿四頭筋との連動が期待でき、インナーとアウターの力でタタタッと軽快に階段を駆け上がれるようになる。エスカレーターに運ばれていく人々を尻目にそれができればカッコいいじゃないか?
8.足が速くなり子どもの運動会でヒーローになれる。
かつて100mスプリントの世界記録を叩き出し、「世界最速の男」と呼ばれたアサファ・パウエル。彼の身体能力の秘密を探ったテレビ番組で公開されたのが、大腰筋のMRI画像。日本国内屈指のスプリンターと比べ、その約2倍はあろうかと思われる筋肉の太さに視聴者は度肝を抜かれた。
ひょっとして大記録を残すようなスプリンターはみな大腰筋(腸腰筋)が発達している傾向があるのでは? 答えはイエス。スプリントでは爆発的なパワーで太腿を引き上げた直後に股関節を伸展させる。その繰り返しだ。
立派な腸腰筋なしにはそんな動きは不可能。あなたも今から鍛えれば、かけっこが絶対に速くなる。運動会ですってんころりんのお父さん卒業だ。
9.胸郭が広がって呼吸が深くなる。

自律神経の働きにも関わる呼吸がしやすくなることで、心身ともにリフレッシュ。
骨盤が後傾して猫背になると、肩こりや腰痛だけでなく、呼吸が浅くなるという不具合が生じる。背中が丸くなり頭が前に出ると、肺と心臓を囲んでいる肋骨で構成された胸郭が潰れるからだ。
意外なようだが、実は肺は自らの力で伸び縮みして空気を出し入れすることができない。胸郭に備わった呼吸筋という筋肉が収縮・弛緩を繰り返し、胸郭が縮んだり広がったりすることで初めて呼吸が成り立つのだ。
なので、猫背などの悪姿勢で胸郭が潰れると呼吸筋が十分に機能しなくなり、結果、呼吸が浅くなってしまう。腸腰筋の働きで姿勢が改善されれば胸郭も広がり、大きな呼吸がしやすくなる。精神的なリフレッシュにも繫がるはず。


