異変に気づくことが大事。放っておくと怖い肝臓の病気。
小さなサインを見逃し養生を怠っていると、気付いたときには相当ヤバい状況に……。肝臓の怖い病気・ウイルス性肝炎の症状や治療法を押さえておこう。
編集・取材・文/オカモトノブコ イラストレーション/上田よう
初出『Tarzan』No.893・2024年12月12日発売

教えてくれた人
森勇磨(もり・ゆうま)/神戸大学医学部卒業。救急総合内科や産業医としての勤務から予防医学の必要性を痛感し、YouTube『予防医学ch/医師監修 ウチカラクリニック』を開設。『40歳からの予防医学』など著書多数。
山本健人(やまもと・たけひと)/京都大学医学部卒業。外科専門医、消化器病専門医、感染症専門医、がん治療認定医など。正しい医学情報を一般にも分かりやすく解説し、近著の『すばらしい医学』はシリーズ累計23万部に。
ウイルス性肝炎|国内で多いのはA〜Cの3種類。
肝炎ウイルスはA〜E型まであり、国内で多いのは3種類。近年は性的接触による感染が増え、また症状が表れない無症候性キャリアから感染が広がる可能性もある。40歳以上であれば肝炎ウイルス検診を受けておくと安心。
| A型肝炎 | B型肝炎 | C型肝炎 | |
| 感染経路 | 経口(水・食べ物) 性行為 便を介した性行為 |
血液 母子感染 性行為 |
血液 母子感染 性行為 |
| 潜伏期間 | 15〜50日 | 30〜180日 | 15〜180日 |
| 治療薬 | なし | あり | あり |
| ワクチン | あり | あり | なし |
| 特記事項 | 急性肝炎の約4割を占め、ほとんどが治癒する | 性交渉による感染が近年、増加の傾向に | 慢性化しやすく肝臓がの原因で約6割を占める |
A型肝炎|ウイルスに汚染されたものを飲食することで感染する

衛生環境が悪い海外地域では生水や加熱が不十分な食べ物が原因に。頻度は低いものの、貝類など海産物の生食による国内の発生事例もある。
感染した人の便から排出されたウイルスに汚染されたものを飲食することで感染する。性行為での感染もあり得るが、原因として多いのは糞口経路を介したもの。近年では、男性の同性間性的接触による感染が増加中との報告もある。先進諸国でもアウトブレイク(集団感染)が発生するケースがあり、性行動において心当たりがある人は特に注意が必要だ。
初期には発熱やだるさなど風邪に似た症状が出る。続いて下痢、吐き気や嘔吐、頭痛、筋肉痛などが表れ、重症の場合は黄疸が出て入院が必要になることも。ただし発症するのは急性肝炎のみで、慢性化するケースはない。
A型肝炎そのものを治療する薬はなく、安静にして静養することで自然治癒する例がほとんど。
B型肝炎|自然治癒するケースも多くあるが、ウイルスを完全に排除するのは不可能
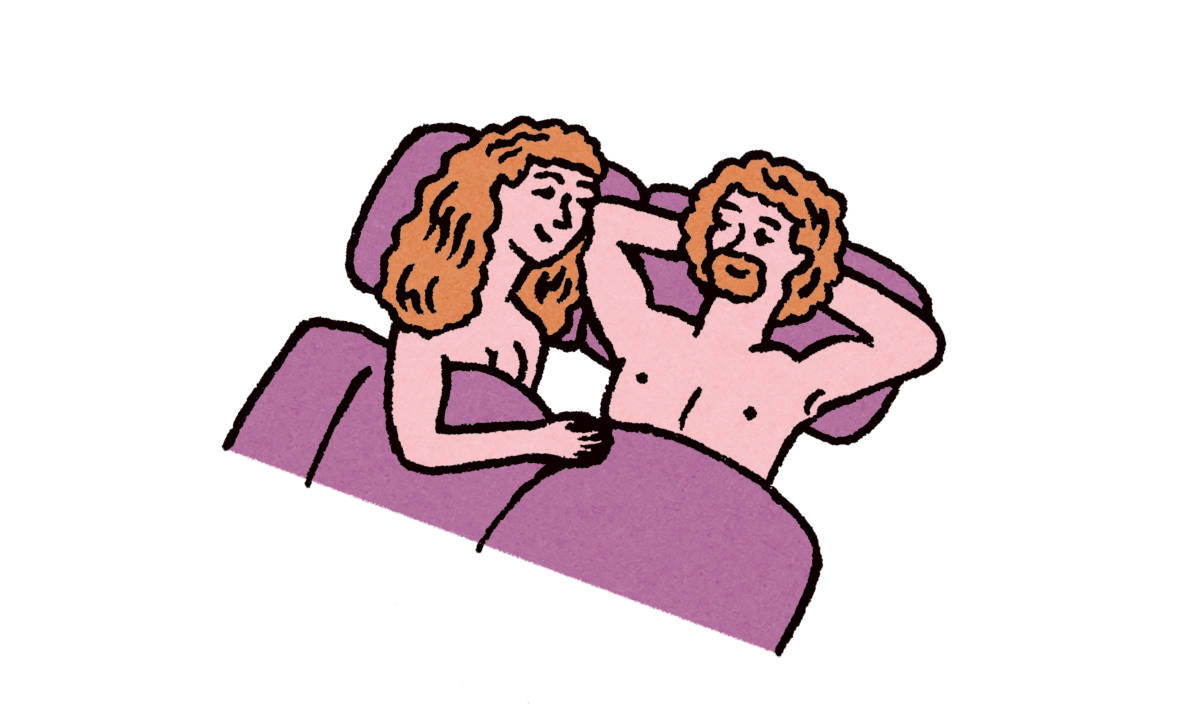
近年、増加傾向にあるのが性交渉によるB型肝炎の感染。避妊具の不適切な使用・不使用、不特定多数との性交渉などがリスクになりやすい。
おもに血液や体液を介し、感染経路は2種類。出産時の母子感染による「垂直感染」は1980年代にワクチンなどが普及して以後は激減。一方の「水平感染」は、性的接触、歯ブラシやカミソリの共用、不衛生な状態での注射、ピアスの穴開け、刺青などが原因に。近年では、成人の急性B型肝炎の多くが性感染とされる。
水平感染の場合、20〜30%は頭痛、発熱、倦怠感などを伴う急性肝炎を経て、残りは無症状のまま自然治癒する。ただし発症すると約10%は慢性肝炎へ、放置すると肝硬変・肝がんへ移行する可能性も。また慢性肝炎は母子感染からの発症が多く、免疫機能が発達した思春期以後に肝炎を起こすと、うち約10%で慢性化する。
ウイルスの増殖を防ぐ飲み薬「核酸アナログ」、ウイルスへの免疫力を高める注射薬「インターフェロン」があり、両方を併用する場合も。ウイルスを完全に排除することはほぼ不可能で、慢性肝炎の沈静化が治療の主たる目的となる。
C型肝炎|感染に気付きにくく慢性化しやすいが、新薬の登場で完治が目指せるように

肝臓がんの原因で約6割を占めるが、感染に気付きにくく慢性化しやすいのがC型肝炎の怖いところ。早期の発見・治療が何より重要だ。
かつては感染源に輸血や血液製剤などの医療行為があったが、ウイルス検査が普及して以後の現役世代で発生は見られない。感染は血液や体液を介し、垂直感染(母子感染)と水平感染(不衛生な状態での注射、カミソリの共用、性行為など)があるのはB型肝炎ウイルスと同様だ。ただしB型に比べて感染力は弱く、原因や感染時期が不明な場合も多く見られる。
潜伏期間を経て急性肝炎を発症しても20〜40%は自然治癒し、何となくカラダがダルい程度で気付かないことも多い。ただし問題は症状が表れなくても感染者の約60〜80%が慢性肝炎に進んでしまうこと。進行も非常に遅く、自覚症状がないまま数十年単位で肝臓の線維化が進み、慢性肝炎のうち30〜40%が肝硬変へと移行する。
なるべく早い段階でC型肝炎ウイルスを排除し、肝硬変や肝がんに進行させないことが重要。かつてはインターフェロンの注射を基本としたが、現在はDAA(直接作用型抗ウイルス薬)という飲み薬が治療の中心に。免疫に作用するインターフェロンは副作用が強く十分な治療効果も得られなかったが、直接ウイルスに働くDAAはカラダへの負担が少なく、患者の95%以上でウイルスを除去し完治を目指せるようになった。
肝硬変|進行を改善する治療法がない。

腹水は肝硬変で最も多く見られる合併症。利尿剤を使って減らすほか、大量の場合はお腹に針を刺して抜く治療が行われる。
慢性的な肝炎で細胞が線維化する肝硬変は、自覚症状がない初期のうちに肝炎の原因を取り除くことが重要。症状が進むと、治療として行えるのは腹水など合併症に対する対症療法のみとなる。
肝臓の解毒能力が低下してアンモニアなどの有害物質や老廃物が脳の神経細胞を破壊するのを防ぐため、アンモニアの吸収を防ぐ薬なども用いられる。
肝臓がん|ラジオ波や抗がん剤の注入で切除しない治療法も。
がんはもはや“不治の病”でないけれど、下の表を見れば早期発見が重要なのは一目瞭然。現在、行われている治療法と併せて見ていこう。
ステージ別・肝臓がんの10年生存率
| ステージ1 | 34.0% |
| ステージ2 | 20.5% |
| ステージ3 | 7.4% |
| ステージ4 | 1.0% |
| 全体 | 22.6% |
データ出典/国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計報告書」より
飲酒の影響も大きいが、実は日本人の肝臓がんの約90%はB型・C型の肝炎ウイルスが原因によるもの。肝機能の状態や進行度によるが、治療は外科的な「肝切除術」のほか、切除せずにラジオ波でがんを焼き切る「焼灼療法」が2004年に保険適用され、急速に普及している。多発・再発が多い肝臓がんでは、抗がん剤を注入してから肝動脈をふさぐ「肝動脈化学塞栓療法」も主流の一つに。


