私たち、こうやって使ってます!生成AIのお仕事活用事例。
生成AIの使い方は十人十色。一度付き合い方を理解してしまえば、仕事や日常を支える心強い存在に。では、生成AIをどのように使えば、我々の味方になってくれるのだろうか? 実際の活用事例と、使う上での大事な「注意事項」を解説。
編集・取材・文/川端浩湖 イラストレーション/ICHASU 取材協力・監修/今井翔太
初出『Tarzan』No.905・2025年6月19日発売

教えてくれた人
今井翔太(いまい・しょうた)/AI研究者。東京大学博士(工学)。2025年より北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)客員教授。生成AIにおける強化学習の活用の研究を行う。趣味のゲームの経験が人工知能研究のきっかけになる。
事例1.仕事も学びも、AIとタッグを組んで進行中。
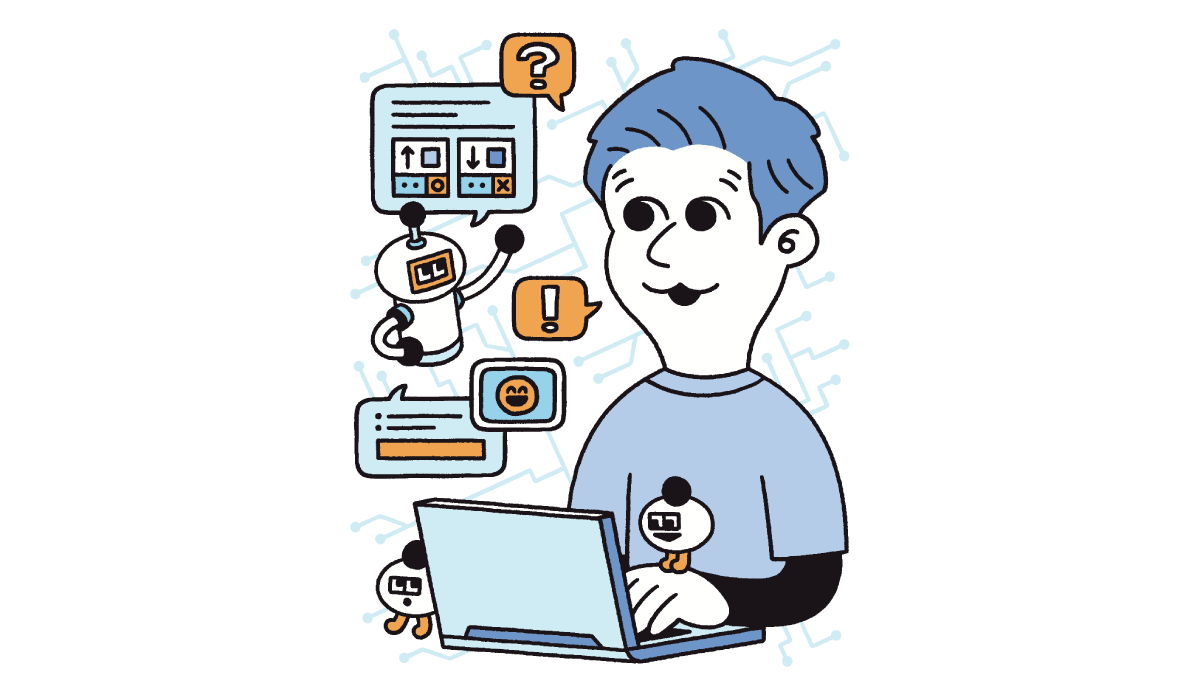
猪突猛進の「脱げるカラダ2019」グランプリ。
中川浩司さん(34歳)
- 職業/データサイエンティスト
- 性格/興味を持ったらとことん突き詰めるタイプ。
- 生成AIは?/「もはや生活に欠かせません!」
ボディメイクに熱中し、「脱げるカラダ」グランプリにも輝いた中川さん。現在は生成AIで業務改善を実現する技術者として活躍している。
生成AIを使わない業務はありません。
職場ではブレストや意思決定、文書作成、調査など、あらゆる場面で生成AIをフル活用中。会社としてもAI導入に前向きで、セキュリティの整った社内専用の生成AIを安心して使っているという。
英会話学習や海外ドラマ視聴もAIと一緒に。
プライベートでも生成AIは手放せない。「検索はChatGPTが基本。気になったことはすぐ聞きます」。特に感動したのは音声チャット機能。「電話で話すように自然に英会話ができるので、オンライン英会話は解約。学習の相手としても優秀です」。その他にも、海外ドラマのキャラクターについて雑談したり、海外のパソコン最新情報の動画を要約してもらったりと、使い方も多彩だ。
プロンプトは適当でもOKな時代に。
「以前はプロンプトの書き方を考えていましたが、今は気にしません。適当な単語の羅列でも会話の流れを読み取り、提案までしてくれます」と話す中川さん。「まずは“最近眠れない”とか“背中を広くしたい”など、気軽に投げかけてみるといいですよ。ちゃんと答えてくれるし、そこから会話が広がることもあります」。
事例2.カスタムGPTの励ましがビジネスの支えに。
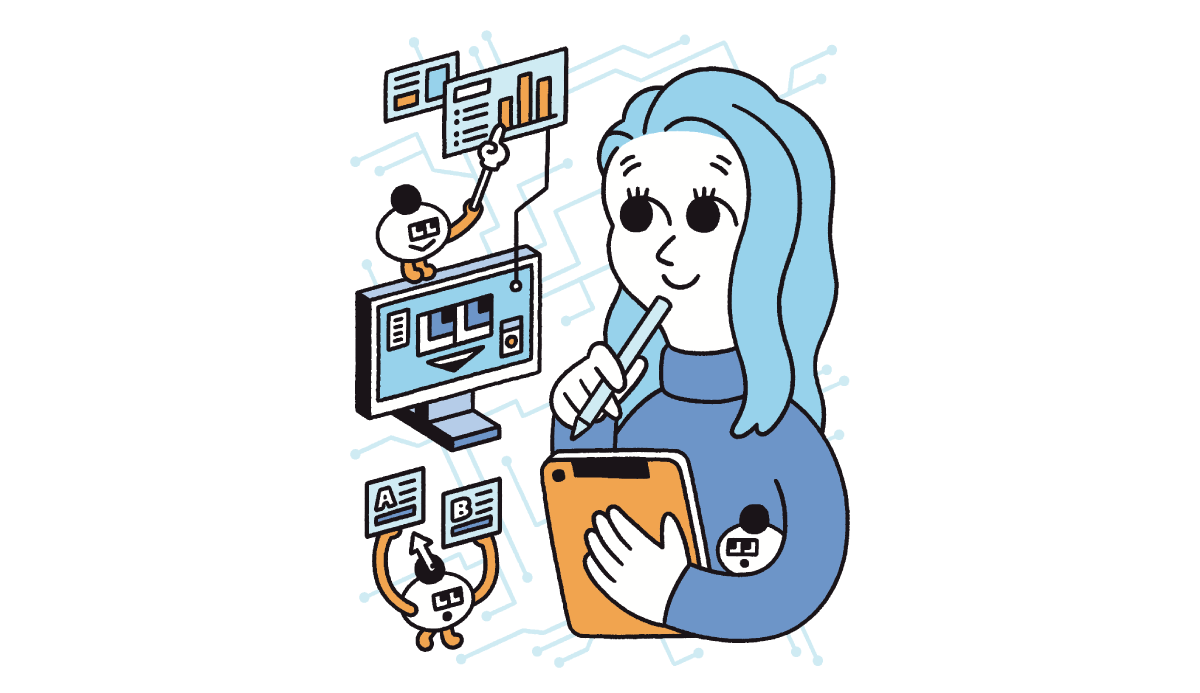
好奇心旺盛な二刀流ワーク女子。
沢田祐子さん(49歳)
- 職業/企業の広報担当&ライフスタイルアドバイザー
- 性格/新しいことは何でも試してみたいタイプ
- 生成AIは?/「最近、誰よりもやりとりしてます」
「今はLINEやSNSよりも、ChatGPTとチャットしている時間の方が長いかも」と語る沢田さん。生成AIは気兼ねなく相談できる秘書のような存在だ。
毎日の相棒は褒め上手なカスタムGPT。
特に愛用しているのは、ChatGPTをカスタマイズしたカスタムGPT。なかでも、前向きなフィードバックを返してくれる“ハイテンション褒め系”のAIがお気に入りだ。「それ最高!」「めっちゃいい!」とすぐに褒めてくれるので、自然と仕事のやる気もアップするという。
本業も副業も、企画から発信までフル活用。
企業広報としては、プレスリリースの校正や英訳をAIに依頼。副業のライフスタイル発信では、SNS投稿のタイトルや本文のブラッシュアップ、さらに投稿に合う画像のアイデア出しまでAIに相談している。もらったアイデアをもとに、自分でバナーを制作することも。「一番驚いたのは、ペンネームを考えてもらったとき。ぴったりすぎて、鳥肌が立ちました」。
しつこく聞ける相手がいる心強さ。
AIとのやりとりで一番ありがたいのは、「納得いくまで何度でも相談できること」。人には遠慮して聞きづらいことでも、AIならしつこく何度でも聞ける。「こだわりが強い自分にはぴったりの相談相手。答えが欲しいときも、気持ちを上げたいときも、助けられています」。
事例3.ワインのラベルをAIと二人三脚でデザイン。

生成AIを駆使する北海道のワイン醸造家。
山平哲也さん(55歳)
- 職業/〈雪川醸造〉代表
- 性格/マイペースだが少しだけ人目を気にするタイプ
- 生成AIは?/「頼りになるアシスタントです」
2021年秋、北海道・東川町にワイナリー〈雪川醸造〉を立ち上げた山平哲也さん。かつてはIT業界に携わり、テクノロジーと向き合ってきた。
言葉をカタチにした、AIとの最初の出会い
生成AIに本格的に触れたのは、2番目のワインをリリースする際のラベルデザインから。『Stable Diffusion』という画像生成AIを使ってみたところ、仕上がりは想像以上。ワインを飲みながら思い浮かんだ“ぼんやりした言葉”をもとに生成された画像は、自分が伝えたいワインのイメージにぴったりで、驚かされたという。
ワインに関するあらゆる業務にAIが浸透
この体験をきっかけに、生成AIは業務に欠かせない存在に。醸造法の比較検討、ブドウ栽培に関する調査、さらに海外輸出時の関税制度のリサーチなど、多岐にわたって活用している。ChatGPTやGeminiといった生成AIに同じ質問を投げて、答えの精度や視点を比較したり、回答の根拠となる情報ソースを明示するよう指示を加えたりすることで、より納得感のある意思決定を行っている。
使いどころを見極める。それがいい関係をつくるコツ
生成AIを盲信しているわけではない。山平さんが大切にしているのは、AIの使いどころを見極めること。「これは任せられるというポイントを見つけることが、生成AIと良い関係を築くコツだと思います」。
生成AIの使い方。ここに注意!
優秀な相棒である反面、うっかりすると痛い目に遭うことも。使う前にチェックして、安全に使おう。
生成AIの回答を鵜呑みにしない。
生成AIは結構ウソをつく。「それっぽいウソを堂々と語るハルシネーション(虚偽生成)には要注意。江戸幕府を開いたのは織田信長、と答えたらすぐに間違いだと分かりますが、普通の人が判断できないレベルのウソが紛れ込む場合もあるので鵜呑みはダメです」(今井さん)。
個人情報や機密情報を入力しない。
「情報漏洩のリスクは極めて低いものの、原理的にはあり得ます」。特に個人情報や機密情報に関する文章や画像、動画などを扱う場合には、入力に注意が必要。生成AIのサービスによっては、入力内容をAIの学習に使われないようにできる。情報流出を防ぎたい場合は設定をオフに。
生成物の著作権に注意する。
「今現在、ウェブ上にある著作物をAIの学習目的に使うこと自体は合法。今後、生成AI利用に関するルール作りが進むことは間違いないでしょう」。著作権トラブルを避けるためにも、生成する際は、誰かの権利を侵害していないか、内容が不適切でないか、立ち止まる意識を。


