
教えてくれた人
益崎裕章(ますざき・ひろあき)/琉球大学教授。京都大学医学部卒業後、ハーバード大学客員准教授、京都大学講師を経て現職に。専門は代謝・内分泌病学。肥満研究に長年携わり、最近注目の玄米研究の第一人者でもある。
1.毎日体重を量る。
先月よりも今月、今月よりも来月、ごく微量であっても体重が右肩上がりに増えていたら、入ってくるエネルギーが多くなっているか消費するエネルギーが少なくなっているか、もしくはその両方だ。
あなたがもし相当量の筋トレを継続していなければ、増えた分の体重はすべて内臓脂肪か皮下脂肪。というわけで共通ルールの基本は毎日体重を計測し、体重変化のベクトルを把握すること。
「体重の評価の際は、体組成を加味することも大切です」と琉球大学教授・益崎裕章さん。
「脂肪が増えて筋肉が減った場合、体重変化が相殺されることもあります。ですから体脂肪率や筋肉量を計測することも非常に重要」
定期的にスーパー銭湯や医療機関、スポーツクラブなどで体脂肪率チェックも。
2.カロリーに振り回されない。
自分が口にする食事でどのくらいのカロリーを摂取しているのか、理解しておくことはとっても大事。とはいえ、食品ラベルやファミレスメニューに表示されている数字に敏感になりすぎるのも考えもの。
「その人の体格や身体活動の程度によって必要なカロリーは異なってきます。さらにカロリーがそのまま体重増加や血糖値に反映するとは限りません。同じ100キロカロリーのものを食べても、太る人もいれば太らない人もいます」
カロリーはあくまで目安として。
3.超加工食品を避ける。

今、健康医療の世界で大きな注目を浴びているのが、UPF=Ultra-Processed Food(超加工食品)。天然には存在しない添加物が入った加工食品全般を指す。
「たとえばドレッシングなどに配合されている乳化剤。これを水に混ぜてネズミに継続的に飲ませた実験では、内臓脂肪が増えてメタボに陥るという結果が出ました。乳化剤が腸内環境のバランスを崩して肥満やメタボを招くのです」
つまり、同じ100キロカロリーをスナック菓子とご飯で摂るのとでは結果が異なる可能性は高い。
「天然にはない添加物は人間の消化システムにとって未知のもの。どう反応したらいいか分からず、誤ったレスポンスをしてしまうと考えられています」
毎日毎食超加工食品、はヤバい。
4.惣菜の揚げ物には手を出さない。
夕方のスーパーで値引きシールが貼られている惣菜パック。その中の半分くらいを占めているのがフライに天ぷらといった揚げ物。高カロリーだからダイエットの敵?いや、これはカラダにとって異物という意味での敵。
「時間が経った揚げ物の油は劣化して過酸化脂質という異物を作り出します。カロリー以上に有害な異物を食べるということに。揚げ物は目の前で作られたフライや天ぷらを口にするのが理想」
むろん、コンビニのカツ丼も×。
5.人工甘味料を避ける。
人工甘味料もUPFに含まれる添加物のひとつ。こちらはノンカロリーの甘いドリンクなどに含まれていることが多い。
「人工甘味料はカロリーはゼロですが、糖の輸送体分子の活動を促し、消化管からの糖質の吸収を上げるという作用があります。ハンバーガーとドリンクはノンカロリーにしようと思って飲んでも、より太ってしまうわけです」
ダイエットによかれと思って飲むそのひと口が脂肪を増やすきっかけに。人工甘味料、避けるべし。
6.外食でも自宅でも手作りのものを食べる。

人類が生まれておよそ500万年。ご先祖たちは試行錯誤を繰り返し、どの食べ物と栄養素がカラダに役に立つか否かを見極めてきた。ここ数十年で登場した未知の添加物に戸惑うのは当たり前の話。
「かつて診ていた患者さんで、食べていないのに太っているという人はやはり超加工品を頻繁に食べていました。外食であれ自宅の食事であれ、天然の食材を中心に選んでいただくというのがポイントだと思います」
選択肢がある場合は天然食材を。
7.タンパク質や野菜を先に口にする。
食事で血糖値が急激に上がると必要以上のインスリンが分泌され、うかうかしている間に脂肪が合成されてしまう。これを防ぐためには「食べ順」が有効。糖質が多く含まれる炭水化物を口にする前に野菜やタンパク質食材を食べる。
「とくにタンパク質を先に食べるとインクレチンというホルモンが小腸から分泌され、インスリンが適度に分泌されます。炭水化物を食べるタイミングでインスリンが作用して血糖値の急上昇を避けることができます」
8.未精製品を主食にする。
炊きたての白いツヤツヤごはん。見るからに美味しそうだが、残念なことに精製穀物は本来の底力をすっかり失っている。
「米ぬかや胚芽など未精製の部分には肥満や糖尿病を起こしにくくする機能性成分がたくさん含まれています」
そのひとつが玄米に含まれているγ—オリザノールという成分で、強力な抗酸化作用が期待できる。備蓄米の品質が保たれるのも米ぬかが原料のコメ油が劣化しにくいのもγ—オリザノールのおかげ。
「さらに油脂に対する依存を改善する効果もあります。マウスにγ—オリザノールを与えるとラードのエサより普通のエサを選ぶようになるんです」
揚げ物大好き、ファストフード大好きという人は、ぜひ主食を玄米に切り替えてみてほしい。
9.主菜は豚や牛より鶏や魚を選ぶ。
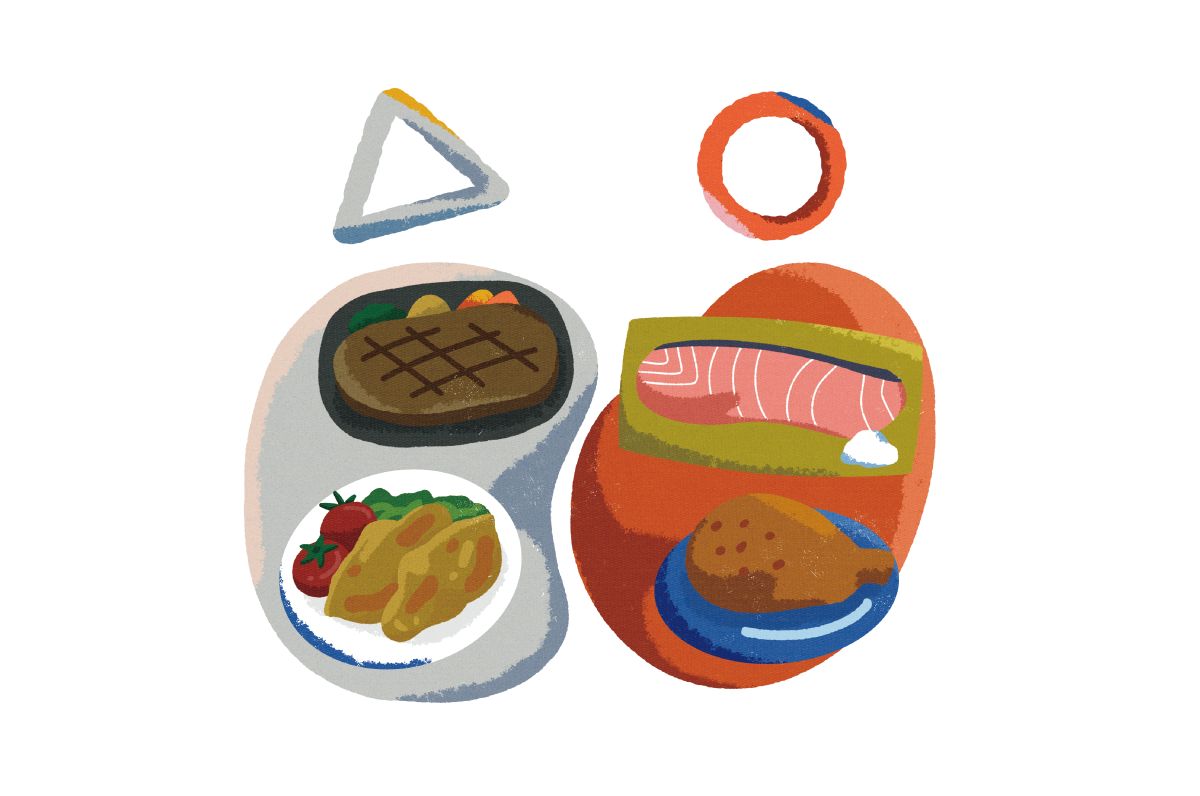
主食は精製タイプより未精製タイプがベター。さらに言えば、主菜は豚肉や牛肉より鶏肉や魚がベターだ。理由は同じ動物性タンパク質食材でも含まれている脂肪酸が異なるから。
「豚肉や牛肉の飽和脂肪酸の中には、インスリンの効き目を阻害したり炎症を起こしやすいパルチミン酸などの脂肪酸が多く含まれています」
週に4、5回牛・豚を食べていたとしたら、頻度をせめて半分に。
10.人と会話をしながら食事をする。
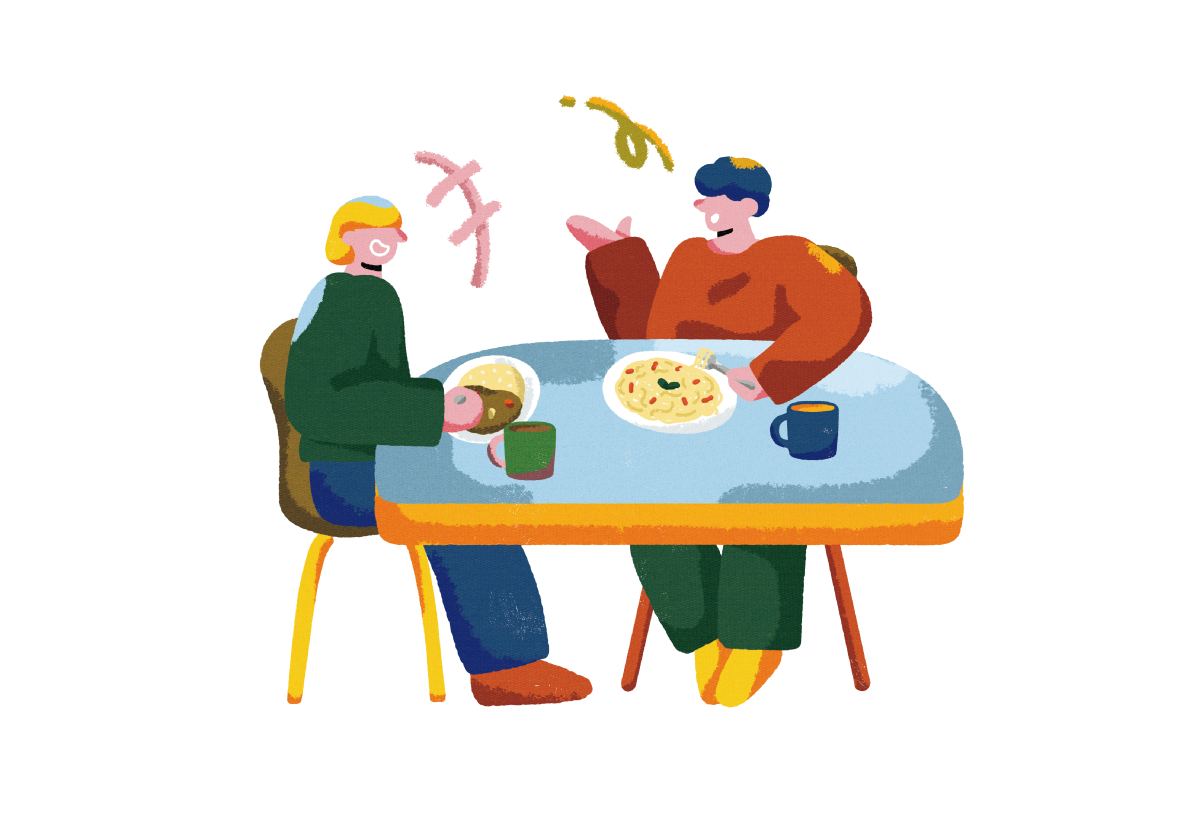
牛丼屋に入ってチケットを買って提供された大盛りの丼を黙々とかき込んで店を出るまでの時間が5分弱。短い、短すぎる。大盛りの丼をスムーズにかき込めるのも、かき込んだ後にコンビニに寄ってスイーツを口にできるのも、すべて早食いだから。
「早食いの人は血糖値が乱高下して空腹感が誘発され、食べれば食べるほどお腹が空く悪循環に。人と会話をしながら食事をする、個食でもゆっくり食べる習慣を」
11.食物繊維が多い食材を毎日食べる。
早食いに陥りやすい理由のひとつは、牛丼やハンバーガーなど柔らかい食品を好むせい。よって嚙みごたえのある食物繊維が多い食事をすることが早食い防止対策に。
「それだけでなく、野菜などに含まれる食物繊維は腸内の善玉菌のエサになります。根菜類などの食物繊維を毎日、できれば毎食食べることは非常に大事なことです」
善玉菌が代謝を助け脂肪を燃やしやすいカラダ作りに役立つことは、もはや周知の事実。せっせとエサやりを。
12.朝食は必ず食べる。

朝食を抜けば、それだけ一日の摂取エネルギーが減る。つまり痩せるチャンスが増える!などという誤情報は即刻修正してほしい。
「朝食を抜くということはカラダが飢餓状態に向かっていくということ。すると血糖値がどんどん下がっていき、その結果、脂肪分解が起きて遊離脂肪酸が血液中に増えます。この遊離脂肪酸は基本的に悪玉物質で、インスリンの効き目を阻害してしまうんです」
インスリンの効きが悪いと昼食後に血糖値が爆上がり。慌てて大量のインスリンが放出されて今度は血糖値がだだ下がり。午後の仕事の最中に舟を漕ぐことになる。これが悪名高い血糖値スパイク。で、脂肪は合成されやすくなり、カラダは糖尿病予備群に向かってまっしぐら。朝食は死守!
13.日常生活ではキビキビ動く。

定期的に運動をしていますという人の中には、運動以外で怠けがちな人がいる。昨日たくさん歩いたから翌日は一日ゴロゴロ。朝ジョギングした日はツーフロア上がるのにもエレベーターを使う。でも、さあやるぞ!という運動ばかりが運動ではない。日常生活活動によるエネルギー消費は結構重要。
「私はスタンディングデスクで一日中立ったまま仕事をします。昼ごはんも立ったまま済ませます」
日常生活にこそ、痩せるチャンスは潜んでいるのだ。
14.夕食後は食べ物を口にしない。
夕食後、夜の10時、11時くらいに甘いものをパクリ、お茶漬けをサラサラ。そんな習慣はただちにストップしてほしい。なぜなら、夜食を食べる人はそうでない人に比べて、膵臓のβ細胞が破壊されている人が多いから。β細胞とはインスリンを合成・分泌する細胞。
「一日三食に適応して働いているβ細胞がアディショナルな食事で酷使されて自殺してしまうことが分かっています」
インスリンが効かなくなるとどうなるか、もうお分かりですね?
15.運動は基本毎日行う。
ダイエットを成功させるファクターは食事と運動、そして睡眠の3要素。このうち優先順位が高いのは食事で、ダイエットの8〜9割を占めるといわれている。ある意味これは正しい。なぜなら、食事コントロールによる減量効果は何より早く表れるからだ。とはいえ、運動をしないでいいかと言えばさにあらず。
「運動をすることでいろんな細胞からエクサカインという生理活性物質が分泌されます。それが皮下脂肪と、とくに内臓脂肪の分解を促すことが分かっています」
ただし、今日エクサカインが分泌されたからといって、その効果は長く続かない。持ち越し効果はないので基本的に運動は毎日行う必要がある。無理? いや、日常生活で階段を上ればいいという話。


