最新! サプリメントの注目キーワード18【後編】
最近なんだかよくわからないサプリメント言葉が増えてきた。だからサプリのトレンドがざっくり摑めるように、仕組みも含めてしっかり解説します。紹介するのは新たな栄養素名だけでなくサプリ先進国のアメリカで「今来ている」ブームも含めた18のキーワード。後編では、フィッシュオイル、グルタチオン、テアニンをはじめ、9つが登場。このうち、あなたが正確な知識を持っているものは果たしていくつある?
取材・文/石飛カノ イラストレーション/Rio Tsuzuki 取材協力/中村泰宏(虎ノ門中村クリニック神谷町院院長)、平井陽子(薬剤師カフェvita代表)、圓尾和紀(管理栄養士、未来日本型食生活協会代表理事)
初出『Tarzan』No.877・2024年4月7日発売

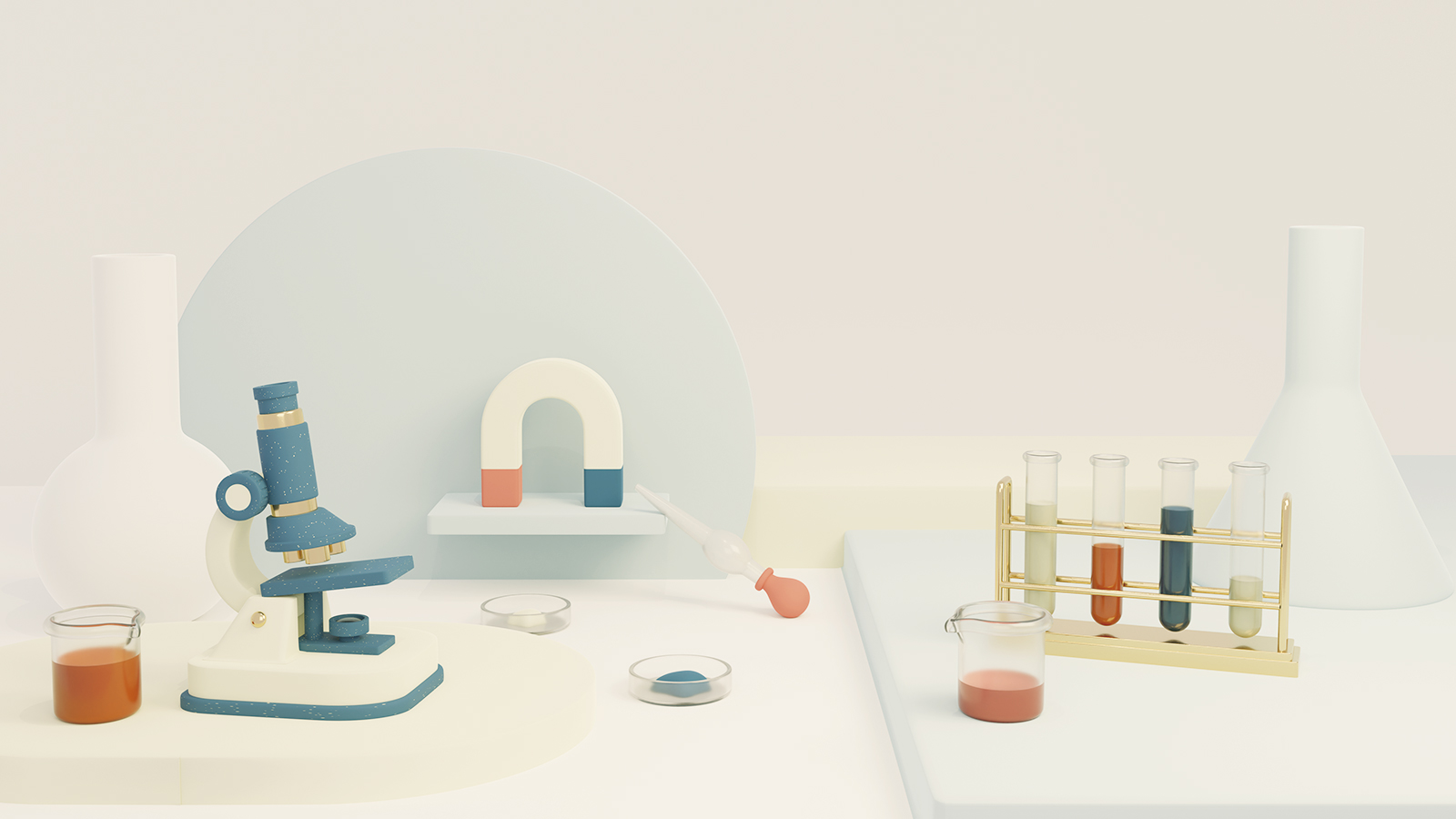
⑩ 若い層を中心に飲みやすさで急成長「グミサプリ」
日本ではまだ数少ないがアメリカではすでに市民権を得ているのがグミの形状をしたサプリ。
「アメリカのサプリメントは粒が大きいので子どもや高齢者が飲み込みにくいことがありますが、グミなら嚙んで嚥下しやすいというメリットがあります。若い人にも口寂しいとき間食代わりにグミのビタミンCを齧る、という感じで取り入れられています」(中村さん)
グミというフォーマットは錠剤に代わって急成長を遂げていて、若者を中心に今最も売れているフォーマットだという報告もある。さらに、中村さんによれば、面白いのがアメリカのビジネスパーソンのランチボックスだという。
「タッパーの中にいろいろなグミサプリとナッツ、バナナ、リンゴなどの果物を入れて、仕事をしながら食べている人もよく見かけます」
グミ→ナッツ→リンゴ→グミ→グミ→バナナ…日本のランチ風景とはだいぶ異なるが、実際これが米ビジネスパーソンの健康の秘訣らしい。
⑪ 脂肪肝改善のツールとして信頼度は絶大「フィッシュオイル」
アメリカではとにかくフィッシュオイルが大人気。魚食の習慣がないこともあり、さまざまな目的でサプリメントから魚油が摂取されている。たとえば中性脂肪の低下、認知症予防、炎症反応の抑制などなど。
「目的のひとつには脂肪肝対策もあります。日本もそうなりつつありますが、アメリカでは脂肪肝が急増しています。普通に食べ過ぎて肝臓に脂肪が蓄えられるケースと、ダイエットで糖質を減らして急に糖質を摂って肝臓で脂肪が合成されてしまうケースがあります。でも脂肪肝の治療法というのはないので、そこでフィッシュオイルで対策しようという流れになっています」(アメリカの健康事情に詳しい医師の中村泰宏さん)
アメリカの食事はどうしても肉食中心なので飽和脂肪酸が蓄積される。これを魚由来の不飽和脂肪酸に置き換えて、結果的に脂肪肝を減らすという目論見だ。
魚食文化を持っている日本人も魚食量が肉食量に追い越されて久しい。そしてアルコールを飲まない人の脂肪肝も増えている。いずれフィッシュオイルサプリが必須になるかも。
⑫ マルチな機能を兼ね備える大人気ペプチド「グルタチオン」
グルタチオンはグルタミン酸、システイン、グリシンという3つのアミノ酸が繫がったペプチド。ヒトの体内では肝臓や皮膚に多く存在し、解毒作用や美白・美肌作用、強力な抗酸化作用などさまざまな機能があることで知られている。
ただ、グルタチオンは医薬品成分に定められているため、サプリメントとしての販売は認められていない。一方、アメリカではその強力な抗酸化作用によってアンチエイジングサプリとしての支持を得ている。
「グルタチオンはすごくいい成分です。アルツハイマーの予防にも効果が期待できるという話もあるし、肝臓の炎症を抑える働きもあります。ただ、グルタチオンがあまりに人気で今は医薬品としての販売が追いつかない状態です。私のクリニックでももう2年間くらい医薬品のグルタチオンが入ってきません。アメリカのサプリでかろうじて手に入るという感じです」(中村さん)
それほどの人気なら、将来、日本でサプリが販売される日も近い?
⑬ フィッシュオイルの新たな可能性が開かれた「LPC-DHA」
一般的なフィッシュオイルサプリに含まれているオメガ3脂肪酸のDHAはTAG-DHA(トリアシルグリセロールDHA)と呼ばれるもの。この形ではカラダの他の部分には供給されても目の網膜には到達しない。ところが視覚障害のある人の網膜はDHAレベルが異常に低いことが分かっているという。
「DHAは脂質異常症などの病気の医薬品になっているくらいの成分。それなら今度は網膜に届けようという研究がイリノイ大学で行われました。研究の結果、化学構造が異なるLPC-DHA(リゾリン脂質型DHA)というものが作られ、動物実験では網膜のDHA含有量が96%に改善されたという結果が報告されています」(アメリカのサプリ業界を研究している薬剤師の平井陽子さん)
実用化されれば、アルツハイマー病や糖尿病、加齢黄斑変性症など、さまざまな病気に由来する視覚障害の改善が図れる可能性もある。
「今後、こういう形で新しいDHAの可能性が開けるかもしれないと感じたニュースでした」
⑭ アメリカで大人気の「コンブチャ」の正体は?「プレバイオティックソーダ」
アメリカで言う「コンブチャ」は日本のそれではなく、紅茶に酵母菌やサトウキビから作った砂糖などを混ぜて作られた炭酸飲料。かなり前から人気を得ている飲料で、目的は善玉菌を腸に届けるプロバイオティクス。アメリカ人はもともと炭酸飲料好き。そこに健康志向がプラスされたのがコンブチャなのだ。
さらに、最近では〈ヘルス・エイド〉というコンブチャ専門メーカーが腸内環境改善を目的とした、良質な食物繊維やリンゴ酢などを配合した新たなプレバイオティックソーダ《SunShip》を開発。ここ数年はプレバイオティックソーダの開発が激化し、続々と新商品が登場している。
「消費者が飽きないようリンゴ味やジンジャーレモン味などいろんなフレーバーがあります。健康意識があまり高くない人はまだ砂糖がどっさり入った炭酸飲料を飲んでいますが、ちょっと意識の高い人はこちらを選んでいると聞いています。どうせ炭酸飲料を飲むならカラダにいいものを、という感覚ではないでしょうか」(平井さん)
⑮ 緑茶の成分がストレス緩和と睡眠改善を促す「テアニン」
緑茶に含まれる主な水溶性成分はカフェイン、カテキン類、そして旨味成分のアミノ酸・テアニン。このうち常に注目を浴びてきたのは抗酸化や血糖値の上昇抑制、脂肪蓄積抑制などマルチな作用が期待できるカテキン。ところが今、サプリメントの成分としてテアニンが静かなブームになっているという。
「テアニンに期待できる作用は、脳に働きかけてリラックス状態を促したり、睡眠の質を改善したり、学習や記憶、集中力を向上させるといったものです。去年、睡眠の質を上げるという乳酸菌飲料が大ブレイクしましたよね。
ということは、睡眠やストレスに関する悩みを持っている人が多いということだと思うんです。そう考えるとテアニンは日本人に馴染みの深い緑茶の成分なので手軽で身近に感じられるんじゃないかと思います」(海外サプリにも詳しい管理栄養士の圓尾和紀さん)
実際に機能性表示食品のテアニンサプリやゼリー状のテアニン製品も登場している。乳酸菌の次は緑茶成分ブームがやってくる?
⑯ ミトコンドリア内で今こそ真の実力を発揮?「α-リポ酸」
α-リポ酸はエネルギーを作り出すミトコンドリア内で働く補酵素のこと。ミトコンドリアのエネルギー産生を助け、体脂肪の増加を抑制する作用があるといわれている。
実は2000年代初頭、α-リポ酸は某健康番組で“痩せる成分”として取り上げられちょっとした話題となったが、ブームは一瞬、すぐに忘れ去られてしまった。誤った健康情報のとばっちりを受けた形だ。
「 CoQ10もそうですが、このα-リポ酸も医薬品としても活用されている人体に有用な成分。一般の人からしたら“ちょっと古い”と言われるかもしれないですけど、長年研究されてきている成分にもっと注目してもいいと思います。
たとえば、α-リポ酸とL-カルニチンを組み合わせると、老化に伴う酸化ストレスが軽減され、エネルギー産生を促すことが新たな研究で発表されています。NMNブームでミトコンドリアに注目が集まっている今、α-リポ酸の老化抑制に関わる作用を深掘りしていきたいですね」(平井さん)
⑰ 「ビタミンK」は骨の強化だけでなく、がんや血糖値にも影響
おそらくビタミンの中で最も影が薄いのがビタミンK。敢えてそのマイナービタミンに注目しているという圓尾さん。
「ここ数年、ビタミンDが注目されていると思うんですけど、同じ脂溶性ビタミンのビタミンKもいろいろ面白いことが分かってきているんです。たとえば、がんの予防や血糖値のコントロールに関わっていることが報告されています」
もともとビタミンKの働きとして知られていたのは骨の形成を助けるというもの。骨の中のオステオカルシンというタンパク質を活性化し、カルシウムの骨への沈着を促すため、カルシウムの吸収を促すビタミンDとセットで骨を強化すると考えられてきた。ところが、単独でも結構いい仕事をすることが分かってきた。
「ビタミンKはあまり不足しにくい栄養素というのも影が薄い理由だと思います。でもサプリで積極的に補給するとより健康効果が期待できるかもしれない。そんな可能性を秘めたビタミンです」
⑱ 日本人の保有率は極めて稀な腸内細菌「アッカーマンシア」
正式名称はアッカーマンシア・ムシニフィラ。2004年に発見された腸内細菌で、肥満や糖尿病、炎症のコントロールなどに関わることが分かっている究極の“善玉菌”だ。
ただ残念なことにこの菌を持っているのは欧米人、とくにヨーロッパ系の人種に多く、日本人では稀。アッカーマンシア菌が腸内細菌の1%を占める日本人は10%程度という調査報告もある。
「そういう菌をサプリメントで補充しても必ずしも腸に定着するとは限らないし、腸内環境が改善するのかは疑問です。ただ、実際私もアッカーマンシア菌のサプリを飲んでいるんですけど結構調子はいいです。論文を見てみると肥満の改善とか腸管のバリア機能改善などの機能が報告されているんですけど、気のせいか便通がいつも以上によくなった気がしています」(圓尾さん)
さまざまな健康効果が期待されている短鎖脂肪酸も然り、腸活も特定の菌にピンポイントで狙いをつける時代に突入。一度、試してみる価値はありそうだ。


