【おやつは洋菓子よりせんべい】冷え性対策のためにできる17のコト
カラダが冷えることなんてしてないですよ、という人。本当にそうだろうか。体温が高ければ問題ないことが、冷えている人にはよろしくないというケースも多々ある。自分の一日を顧みて、温め行動への置き換えを。
取材・文/石飛カノ 撮影/小川朋央 イラストレーション/死後くん 監修/川嶋 朗(東京有明医療大学教授)
初出『Tarzan』No.827・2022年2月10日発売

① 5分間キープで熱を測る

覚醒している時間の中で体温が最も低いのは起床直後。この段階で体温が36度未満なら、本人の自覚がなくともカラダが冷えている可能性がある。よって朝目覚めたときの体温計測をルーティンにするのは正解。
ただし、電子体温計で瞬間的にはじき出される数値は予測体温。腋の下に体温計を5分間程度挟んで出た数値の方が、より精度が高い。朝の5分間を体温計測に充当しよう。
② 毎朝白湯を飲む

朝起き抜けのカラダは軽い脱水状態なので、水分を口にするのは非常にいいこと。ただ、問題はその温度。冷たい水をゴクゴク飲むと当然内臓が冷えてしまう。
おすすめは白湯。温かい白湯を飲むと起きたばかりで働きの鈍い腸管が活性化しカラダに熱が発生、代謝の向上にも繋がる。熱湯ではなく体温より若干高い温度が適温。湯を沸かすのが面倒ならレンチンでもOKだ。
③ 味噌汁と納豆ごはんを食べる
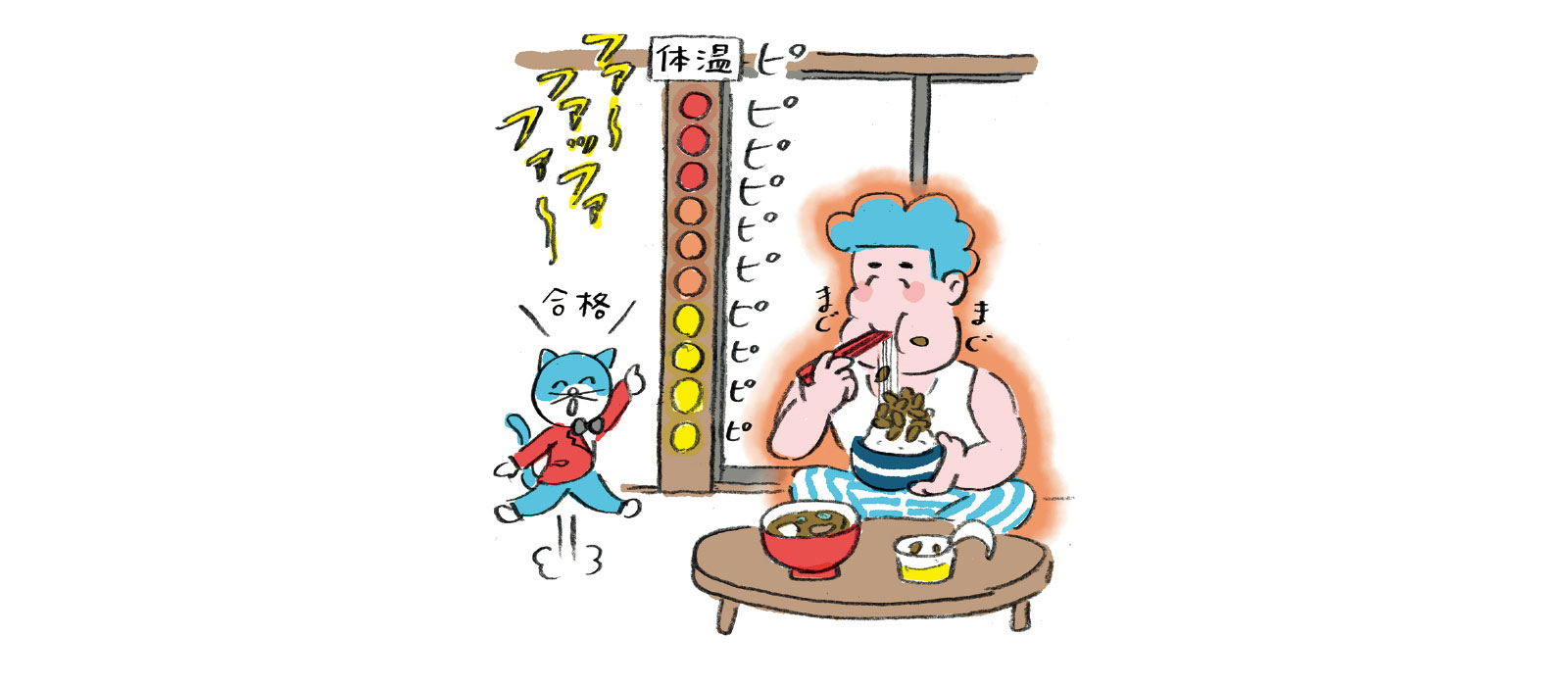
体温は起床前から徐々に上がり始め、午後から夕方にかけてピークを迎える。なので覚醒後の体温を底上げしておくのは非常に大事。そのために欠かせないのが朝食だ。
コーヒー1杯では体温上昇は見込めない。エネルギー源になる糖質をごはんで摂り、消化吸収に手間のかかるタンパク質を納豆で摂る。ここに温かい具入りの味噌汁を添えれば完璧。食事由来の熱が発生して体温はぐっと上昇。

④ 朝シャワーの後はしっかりドライヤー

朝シャワー派で髪洗いっぱなしはNG。濡れた髪が冷やされることでカラダの熱は奪われる。どんなに短髪でもしっかりドライヤーで乾かすこと。
余裕があればその際、ドライヤーでツボを刺激するドライヤーお灸もおすすめだ。狙うツボは内くるぶしから指4本分上にある三陰交。熱風を近づけ熱いと感じたら離す。これを4〜5回繰り返す。
⑤ 3回に1回は階段を使う

筋肉は全身の熱の発生源なので、加齢による筋力低下を防ぐことが冷え対策の基本となる。とくに下半身の大筋群に日常的に刺激を入れるのが効率的。
必ずしもジムに通って筋トレに励まなくてもいい。駅に行けばそこに階段があるはずだ。階段の上り下りはスクワットもしくはランジの動き。エスカレーターをパスすれば、自ずと下半身トレになる。
⑥ 1時間に1度は席を立ってお尻をゆする

良くも悪くも日本人はとても勤勉。会社に出勤し一度デスクに着いたら、必要最低限の用事以外は不動の構え。長時間座り続けることでお尻や腰の筋肉は固まり、血流は滞る。
血液が巡らなければ全身に熱を運べない。で、カラダの末端が冷える。そこで、仕事の合間にタオルを使ってマッサージ。タオルを腰の後ろに回して左右の端を両手で持ち、左右に軽くゆすってお尻、腰の筋肉をほぐそう。
⑦ カレーうどんを食べる

ランチはもっぱら、ざる蕎麦をつるつるっと流し込んで終了。でも体温より冷たいものを口にすれば、カラダは即座に冷える。冷えの自覚があるなら、麺類は温かいものがおすすめだ。
さらに、唐辛子、胡椒、ショウガ、ニンニクなどスパイスや辛味成分を含む食材を活用するとなおよし。蕎麦屋でのベストチョイスはズバリ、カレーうどん。

⑧ 緑黄色の野菜ジュースを氷ぬきで

ランチの後はコンビニに寄って冷たいお茶を買って飲むのが定番。ところが緑茶はカラダを冷やすうえ、キンキンに冷えたお茶はランチで作った熱を帳消しにしてしまう。
カラダを温める食材のひとつは色の濃い緑黄色野菜。よって、もし選択肢があるのなら食後のドリンクはニンジンや小松菜などの緑黄色野菜のジュースがおすすめ。むろん常温で。
⑨ せんべいを食べる

意外なことにものを食べるときよく噛むこともまた、冷えの予防に繋がる。ものを噛むと歯肉の中にある神経から脳に信号が伝わり、脳から神経ヒスタミンという物質が分泌される。
この神経ヒスタミンが満腹中枢を刺激すると同時に内臓脂肪の燃焼を促して体内に熱を発生させるのだ。おやつには柔らかい洋菓子より硬いせんべいをどうぞ。
⑩ スマホを置いて指をいじる

心臓から遠い位置にある部位ほど、血流が滞りやすく冷えやすい。逆に言えば末端部分をほぐして熱を発生させれば、全身の冷えの改善にも繋がるということ。そこで、帰宅後にはスマホをいじる手をちょっと休めて指先のマッサージを。
親指と人差し指を合わせて固定し、人差し指の爪の両端を逆の手でつまんで押す。左右の10指をすべてマッサージした後は指先がぽかぽかに。
⑪ カーテンは床までの長さで二重に
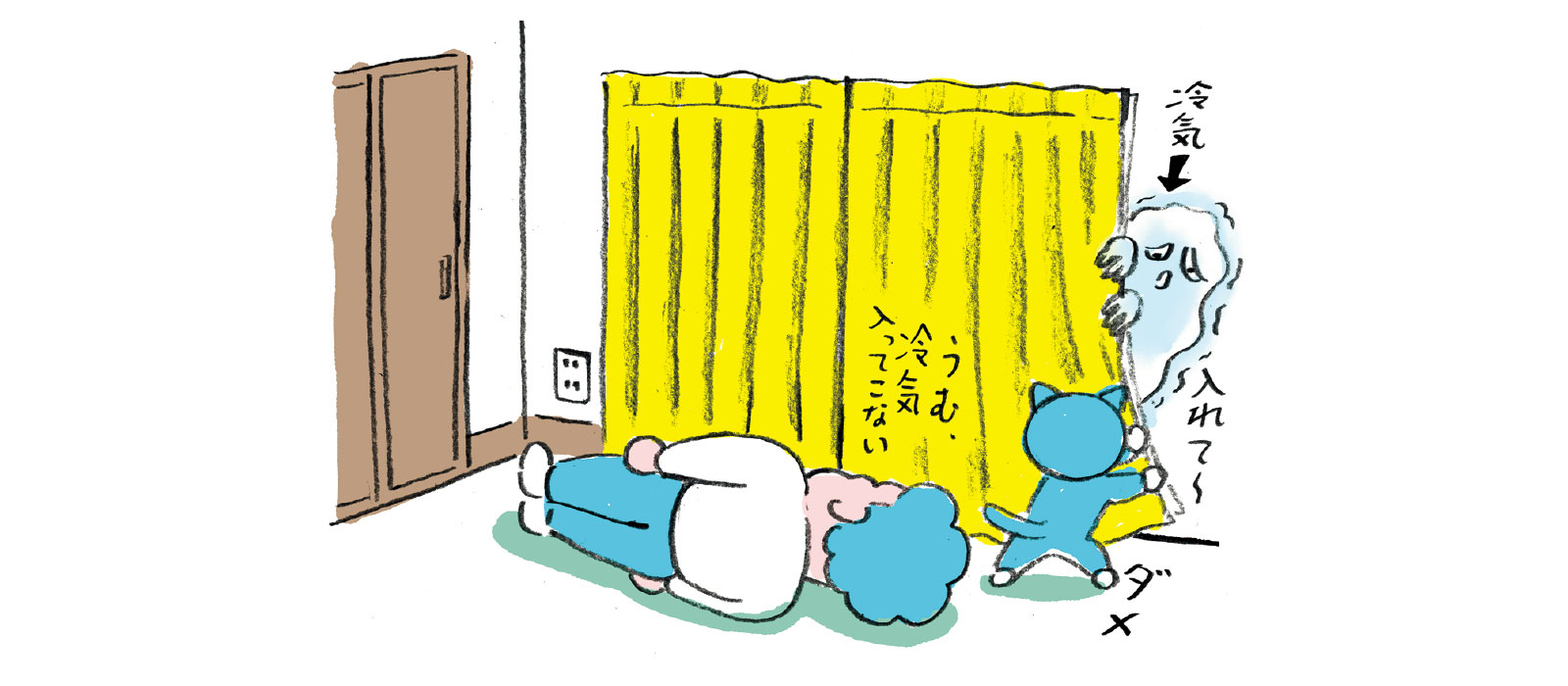
暖房は稼働しているのになぜか薄ら寒いという場合、「コールドドラフト現象」が起こっているかもしれない。これは暖房で温められた空気が窓に触れて冷やされ、そのまま下降して床近辺に流れ込むという現象。
こうなると、たとえ室温が高くても体感的には寒さを感じてしまう。対策としては床までの長さのカーテンを二重に設置し、冷気を阻止して暖気を逃がさないこと。
⑫ 適量の燗酒を飲む

くどいようだが冷蔵庫で冷やされた飲食物を口にするとカラダの内部は即座に冷やされてしまう。よって、いくら血流を促すアルコールとはいえ、真冬に缶チューハイをガブガブ飲むのは厳禁。飲むなら日本酒のお燗がベターだ。
ただし、あくまで1合程度という適量を守ること。アルコールの分解や解毒には水分が使われるのでカラダが脱水状態になり、逆に血流が悪くなるからだ。
⑬ つまみは野菜チップスに

キュウリやセロリなどの夏野菜、大根など色が白っぽいものはカラダを冷やす。これらの集合体で水分の多い野菜スティックはつまみとしては避けた方が無難。
野菜を摂るなら乾燥させたチップスがおすすめだ。ニンジンやレンコンなどの根菜は、もともとカラダを温める食材。ゴーヤやオクラなどの夏野菜は本来ならカラダを冷やす食材だが、水分が抜けたチップス状態なら問題なし。
⑭ 家事でながら運動をする

文明が進歩するのはありがたいことだけれど、その反面、冷えを助長することにもなる。だからこそ、生活の中で運動を取り入れる意識が重要になってくる。
たとえば家事を行いつつの「ながら運動」もそのひとつ。調理中や洗い物をしながら踵を上げ下げしてふくらはぎの筋肉を刺激する、床掃除はモップではなく敢えて雑巾がけをして全身運動を行うなど、機械任せにせず、ひと工夫を。

⑮ バスタブの湯に浸かる

冷えの自覚があるのなら、入浴はシャワーだけで済ませずバスタブにきっちり浸かることがマスト。38〜40度程度の湯に最低でも10分間は浸かって血流を促そう。
その際は炭酸系の入浴剤の有効利用を。皮膚から体内に吸収された炭酸が血管を広げ、より血行を促してくれるからだ。入浴後はもちろんカラダをしっかり拭き、髪も自然乾燥ではなくドライヤーで乾かすこと。

⑯ お風呂上がりに笑えるドラマを見る

寝る前のひととき、テレビやオンデマンド、ウェブ配信でさて何を見る? 冷え対策に徹したいなら、ホラーやアクションやミステリーより断然お笑い系のコンテンツがおすすめだ。
笑うことで自律神経の副交感神経が優位になり、末端の血管が拡張され、カラダが休息モードになるからだ。ちなみに、笑いはNK細胞という免疫細胞の一種を活性化する。冷えで低下した免疫力のサポートにも。
⑰ 羽根布団+毛布で寝る

睡眠中は一日のうちで最も体温が下がるので、カラダを冷やさない寝具の工夫を。寝具の間に空気の層を作ることが暖気を逃がさないコツ。なので、寒い日は羽根布団の上に毛布をかけるのがおすすめ。
電気毛布を使う場合は寝る前に温めておき、寝る際は電気を切る。電気をつけっ放しで寝ると汗をかいて逆に冷えてしまうからだ。さらに、敷き布団を2枚重ねて下からも断熱すれば完璧。