パルクールって最近よく見るけど、そもそも何なの?|パルクールとはなにか①
ここ数年で目にするようになった「パルクール」。SNSや動画サイトなどでよく見かけるけど、実はあんまり、何なのかがよくわかっていない…。そこで今回は、「SASUKE」などテレビでも活躍中、日本パルクール協会会長の佐藤惇さんに「パルクールってそもそも何なの?」を、基本中の基本から聞きます。
取材・文/中野慧 撮影/大内カオリ

よく動画で見かけるパルクールって何なの?
――パルクールって、YouTubeやTikTokなどの動画サイトでも目にしますし、最近ではゲームやライトノベルなどにも登場しますけど、一般的なイメージとしては「高いところからジャンプで飛び降りたり、宙返りしたり…常軌を逸した動きをする人たち」という感じです。そもそもパルクールって何を競っているのでしょうか?

佐藤惇さん/日本で唯一のパルクール指導に特化した会社〈X TRAIN〉共同代表で、日本パルクール協会会長を務める。パルクール実践歴は17年で、国内におけるパルクール指導の第一人者として「YAMAKASI」直伝の精神を基に、パルクールの普及活動を行う。「SASUKE」常連選手であり、Snow ManのCMアクション監修なども行う。
佐藤惇さん(以下、佐藤):そう思われちゃってますよね(笑)。まず知って欲しいのですが――パルクールって、人と競うのではなく「自分自身を高める方法」なんですよ。
――「自分を高める方法」…!? もしかして自己啓発セミナー的なやつですか…!?
佐藤:違います(笑)。もう少し噛み砕いて説明してみますね。パルクールってすごく簡単に言ってしまうと「移動する動きでカラダを鍛えていく」のが目的なんです。
――なるほど。でもスポーツなんだから、ルールはあるはずだし、スタートやゴールもあるはずですよね?
佐藤:いえ、パルクールにはサッカーのようにルールもないので、多くの人がイメージする競技やスポーツともちょっと違います。そもそもスタートとゴール地点を決めるのも自分だし、その移動の仕方、例えばくぐるのか越えていくのか、登るのか、かわすのかも全部自分次第なんですね。
――むむむ…わからなくなってきました。
佐藤:そうだな…。わかりやすい例で言うと、子どもの頃に公園で、遊具やベンチ、柵、壁とかを使って、「地面に落ちずにどこまで行けるかな?」みたいな遊びをするじゃないですか。
――あー、たしかにそういう記憶はあります!
佐藤:パルクールは、そういう発想が根本にあるんです。なかでもパルクールで重要なのは「ジャンプ」です。A地点からB地点まで、地面につかずにジャンプで移動する、ということですね。
――そう言われてみると、ネットで見かけるパルクールの動画は「地面に降り立ったら動画の終わりだな」みたいな感じがありますね。
佐藤:それと、パルクールには『シティハンター』みたいなところもあるんですよ。パルクールをする人のことを「トレイサー(traceur)」と言うのですが、僕たちトレイサーは、街の地理に詳しくて、A地点からB地点に行くときにどういうルートが最短なのか、どういう障害物があるのかを把握していたりします。
――なるほど。『ブラタモリ』のタモリのような地理マニアみたいな感じですか?「おっ、ここに坂が!」とかって、何の変哲もない坂に急に興奮し始めたりとか。
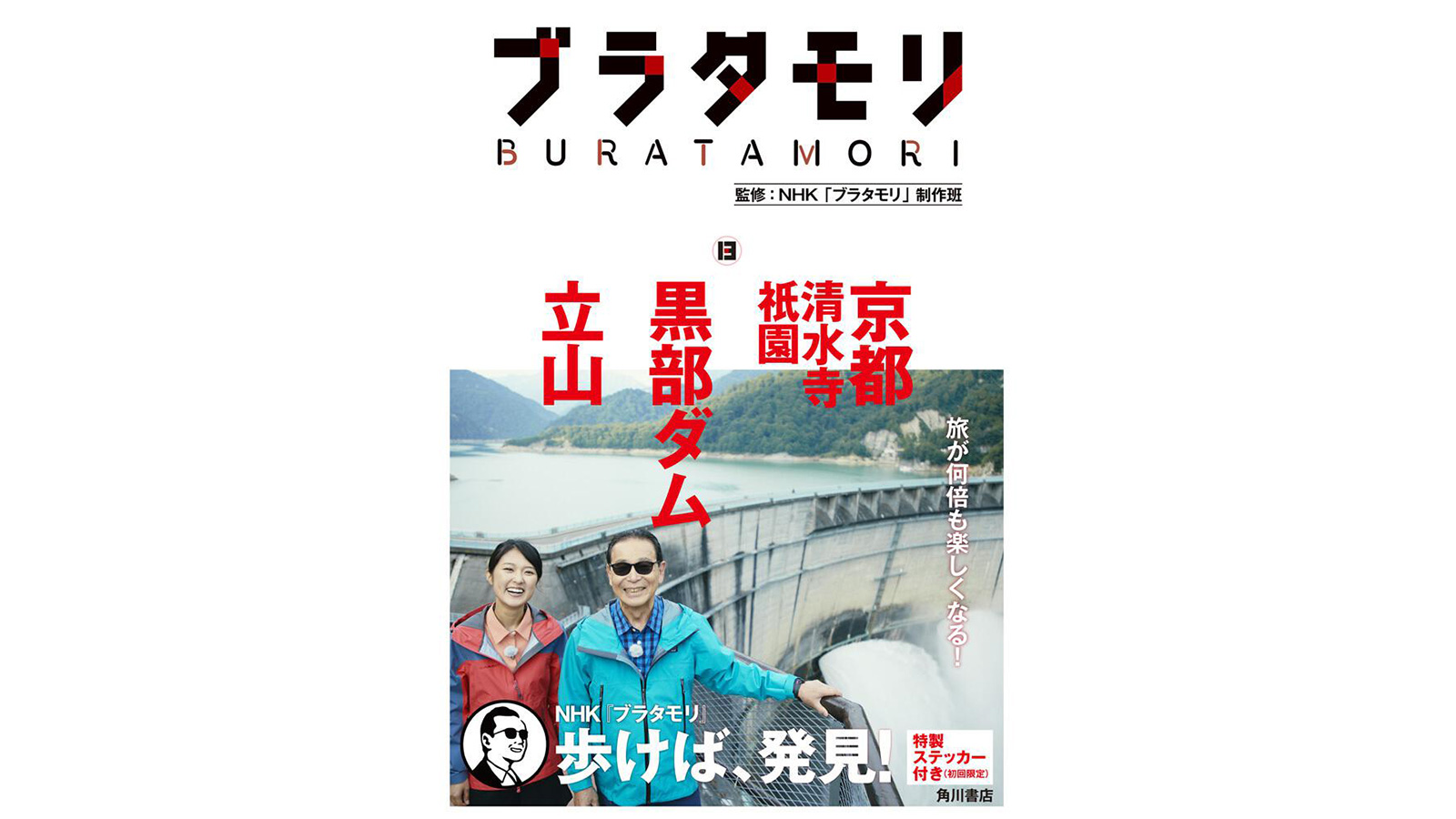
NHK「ブラタモリ」制作班(監修)『ブラタモリ 13 京都(清水寺・祇園) 黒部ダム 立山』KADOKAWA、2018年。https://www.amazon.co.jp/dp/4041073758/
佐藤:そういうところはあるかもしれませんね。僕も坂とか階段とか、壁とか柵を見ると「おっ!」って思っちゃいます。ただですね、パルクールをやる人はそんなタモリさんみたいな側面もありつつ、一方で『ドラゴンボール』の孫悟空やジャッキー・チェンみたいな精神性もありますね。
――それは「最強を目指す」というところですか?
佐藤:はい、そうです。実際にパルクールを始めた人たちって、孫悟空やジャッキー・チェンに憧れていたんです。スパイダーマンとかバットマンとか、自分たちをスーパーヒーローに見立てるような世界観があって、柵が入り組んでいて壁がある場所をあえて突き進んで、自分なりの体の動かし方でどこまで速く、どこまで効率的に動いていけるかを探っていくわけです。
――なるほど、「俺より強い奴に会いに行く」というような、少年漫画的な世界観にドライブされているんですね。
パルクールの歴史① ~2000年:ハリウッド監督リュック・ベッソンのフックアップが歴史を変えた
――なんとなくパルクールがわかってきたんですが…そもそもこれって誰が始めたんですか? 昔からあったスポーツではないですよね。
佐藤:90年代後半頃のフランスが発祥です。ただ、僕らがイメージするような白人のフランス人ばかりではなく、アフリカ系やアジア系移民、混血の人たちも一緒になってやり始めたんです。
――へー! まさに多様なバックグラウンド。
佐藤:フランスってパリみたいな大都会は別にして、郊外には貧しい家庭の人たちが住む住宅地が広がっているんですよ。当然、治安もよくありません。そんな状況のなかで友達や家族を守れるように、今よりも自分が強くなりたいという気持ちが一番にあった。そのときに彼らがイメージしていたのが『ドラゴンボール』やジャッキー・チェンなどのスーパーヒーローだった。そういう究極の状況下で、究極に挑めるようなカラダと心を、外遊びで鍛えていくという発想のなかから、パルクールが形作られてきたんです。
――ハードな状況のなかでいかに生き延びるかという発想から生まれてきたんですね。ただ何となく、パルクールってインターネットの動画カルチャーのなかで育ってきたイメージがあります。
佐藤:ええ、YouTubeなんかはすごく大きかったです。でも、それ以前に映画のチカラが大きかったかもしれないですね。パルクールはけっこう前から映画でフィーチャーされてきたんですよ。
――おお、映画!
佐藤:パルクールが取り上げられた一番古い映画作品はおそらく、『レオン』で有名なリュック・ベッソン監督がプロデュース・脚本を手掛けた『TAXi②(タクシー・ツー)』(2000年公開)です。この映画は基本はカーアクションなんですが、忍者みたいな人たちが出てきて街中を駆け回るシーンが出てきます。その忍者たちを演じたのが、パルクールの創始者であるフランスの「ヤマカシ(YAMAKASI)」というチームなんですよ。
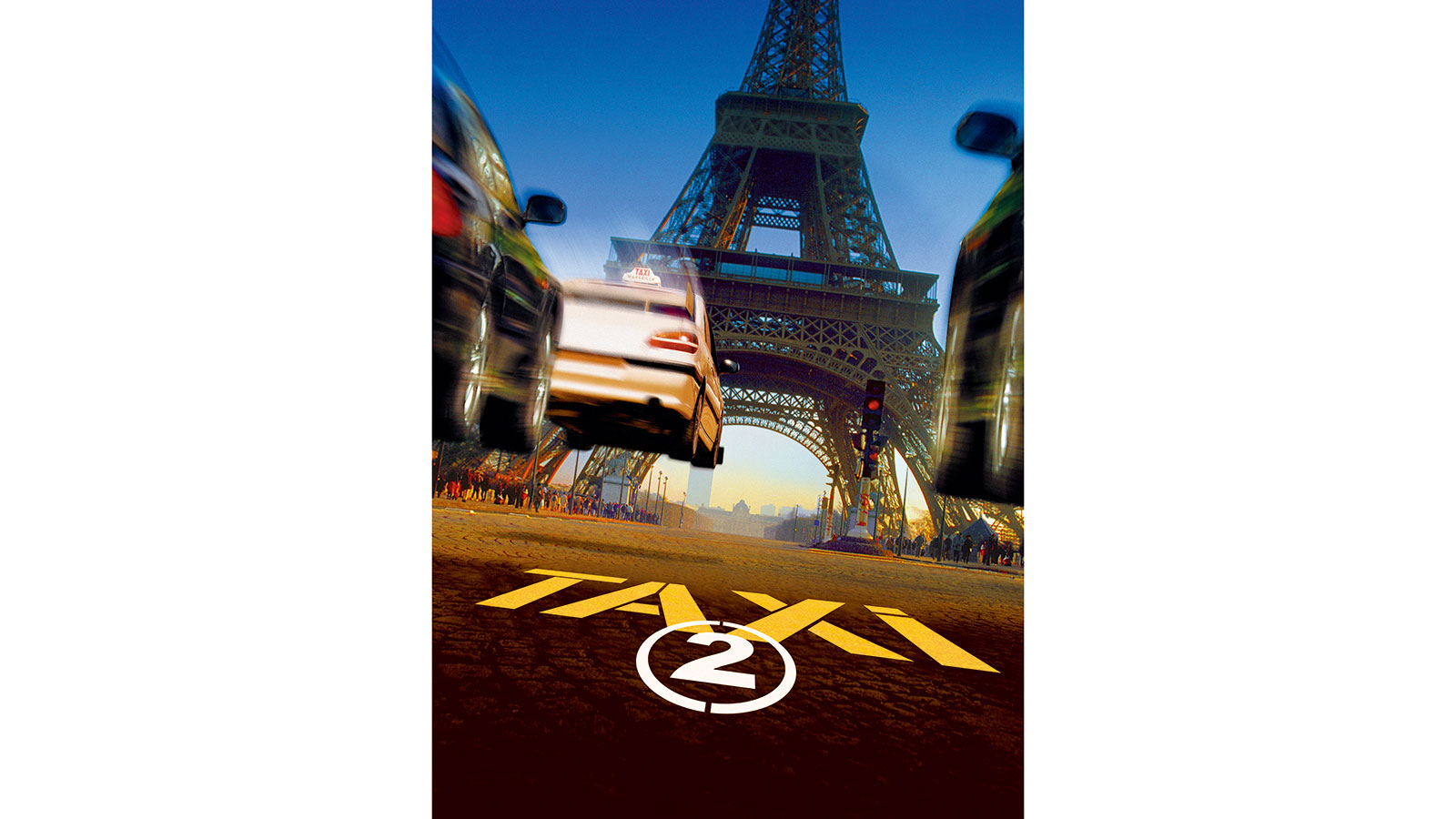
『TAXi②』製作:リュック・ベッソン、ミシェル&ローラン・ペタン/脚本:リュック・ベッソン/監督:ジュラール・クラヴジック、2000年公開、フランス。Blu-ray発売中 Blu-ray:¥2,500+税 発売元:アスミック・エース 販売元:バップ © 2000 EUROPACORP – ARP – TF1 FILMS PRODUCTION(Amazon Prime ※HDレンタル400円/U-NEXT)
フランスのカーアクション映画『TAXi』シリーズ第2作。マルセイユに住むスピード狂のタクシー運転手ダニエルは、恋人であるペトラの両親に挨拶しに家を訪れたところフランス軍高官の父に気に入られ、来仏中の日本の防衛庁長官のドライバーに抜擢される。しかし謎のテロリスト集団に急襲され、長官が誘拐されてしまう。ダニエルは、親友であるマルセイユ警察の刑事エミリアンとともに長官を救出しにパリへ向かうが――?
――「ヤマカシ」って日本語みたいな響きですけど、何か関係があるんでしょうか?
佐藤:いえ、アフリカのコンゴ地域で話されているリンガラ語で、「強靭な人間」や「強靭な精神」という意味の言葉です。ヤマカシのメンバーにコンゴにルーツがある人がいたんですよ。ヤマカシは1980年代から、パリから南に電車で30〜40分ぐらい行ったところにある郊外のリス(Lisses)やエブリー(Evry)という町で、ダヴィッド・ベル(David Belle)やセバスチャン・フォーカン(Sébastien Foucan)といったメンバーが中心になってつくられました。
――ふむふむ。リュック・ベッソンというフランス出身、ハリウッドにも影響力のある映画監督/プロデューサーがパルクールに注目したのは大きかったわけですか。
佐藤:そうですね。リュック・ベッソンは『TAXi②』で出会ったヤマカシのメンバーをすごく気に入って、そのすぐ後の2001年に、それもそのまま『YAMAKASI』という映画をプロデュースしています。これが、世界中にパルクールの存在を広めた一番の出来事だったんですよね。これらの映画で、トレイサーたちの身体能力の凄さが広まったのかなと。
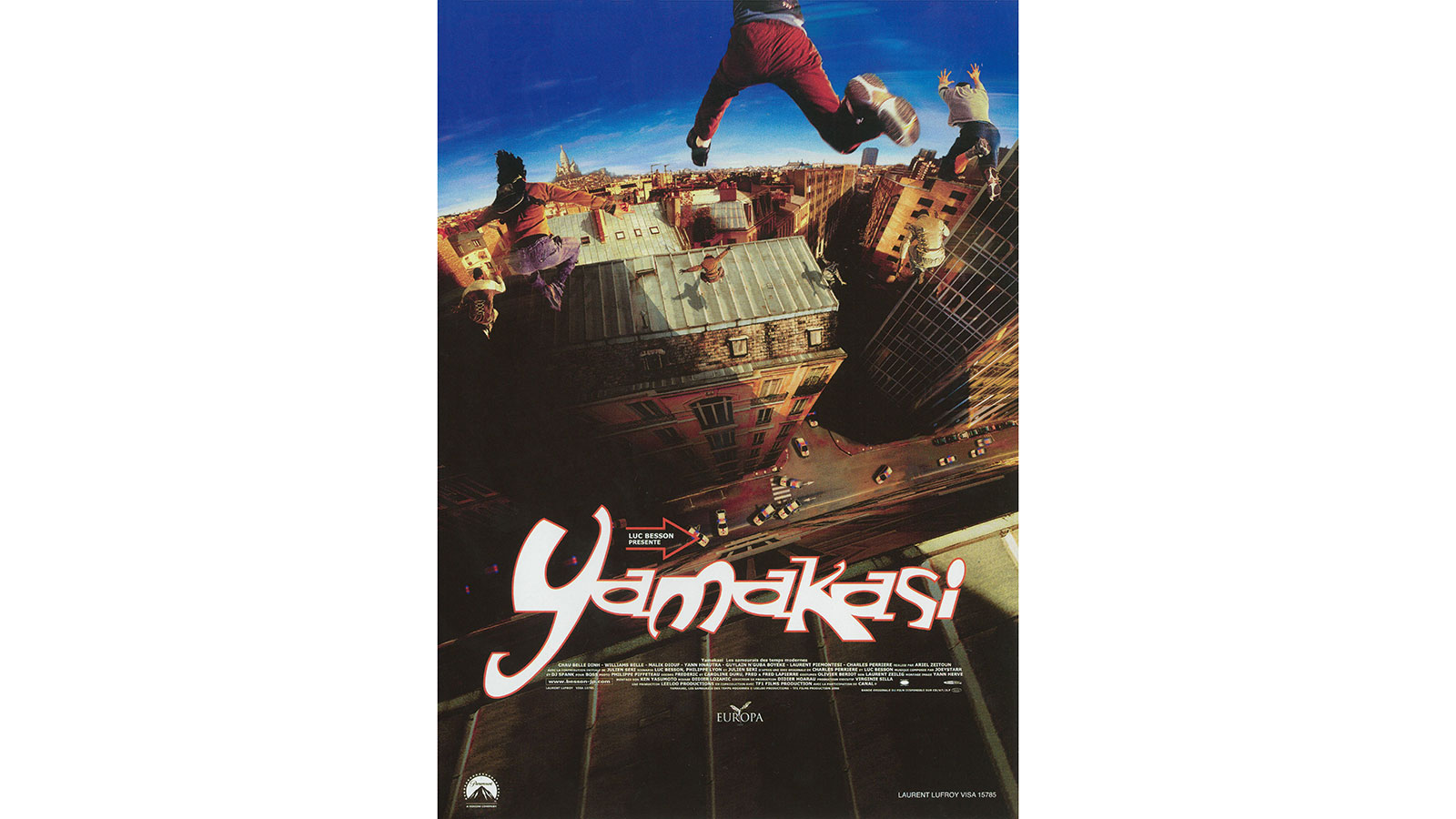
『YAMAKASI』監督:アリエル・ゼトゥン 脚本:リュック・ベッソンほか、2001年公開、フランス。好評配信中 ©2001 EUROPACORP – TF1 FILMS PRODUCTION. All rights reserved(Amazon Prime ※HDレンタル440円/U-NEXT)
フランス郊外の、ビルをよじ登る若者集団「ヤマカシ」。彼らは子どもたちのヒーローとして尊敬される一方、警察にマークされ続けていた。ある日、ヤマカシに憧れる少年ジャメルが木登りをしていて落下してしまい、重傷を負う。高額の費用がかかる緊急臓器移植手術が必要だが、ジャメルの母は十分なお金を用意できない。責任を感じたヤマカシたちはジャメルの命を救うため、ある行動に出るが――?
――面白いですね。正統派の映画史ではあまり知られていない気がしますが、リュック・ベッソンという映画監督がパルクールという身体文化でそんな大きな功績を果たしていたとは。
佐藤:リュック・ベッソンは、その後も数多くの作品でパルクールを取り入れているんですよ。2004年の『アルティメット』という映画にダヴィッド・ベルが出演してアクションシーンを演じたのも大きかったです。しだいにパルクールはハリウッドからも注目されるようになり、どんどん映画に取り入れられるようになっていきました。

近未来のフランスでは、犯罪の多い地域を「第13区」として壁を作り隔離を行っていた。その住民であるレイト(演:ダヴィッド・ベル)は、犯罪組織から麻薬を奪っては処分していた。これに怒った麻薬組織の首領タハによって妹をさらわれ、レイト本人はタハと癒着している警察によって収監されてしまう。6ヶ月後、タハの組織にミサイルを奪われてしまったフランス政府は、捜査官ダミアン(演:シリル・ラファエリ)に「第13区」への潜入を命じる。そのダミアンの道案内人として選ばれたのが、収監中のレイトだった――。なお本作は2014年にハリウッドで『フルスロットル』としてリメイクされ、ダミアン役を『ワイルド・スピード』シリーズのポール・ウォーカーが演じている。
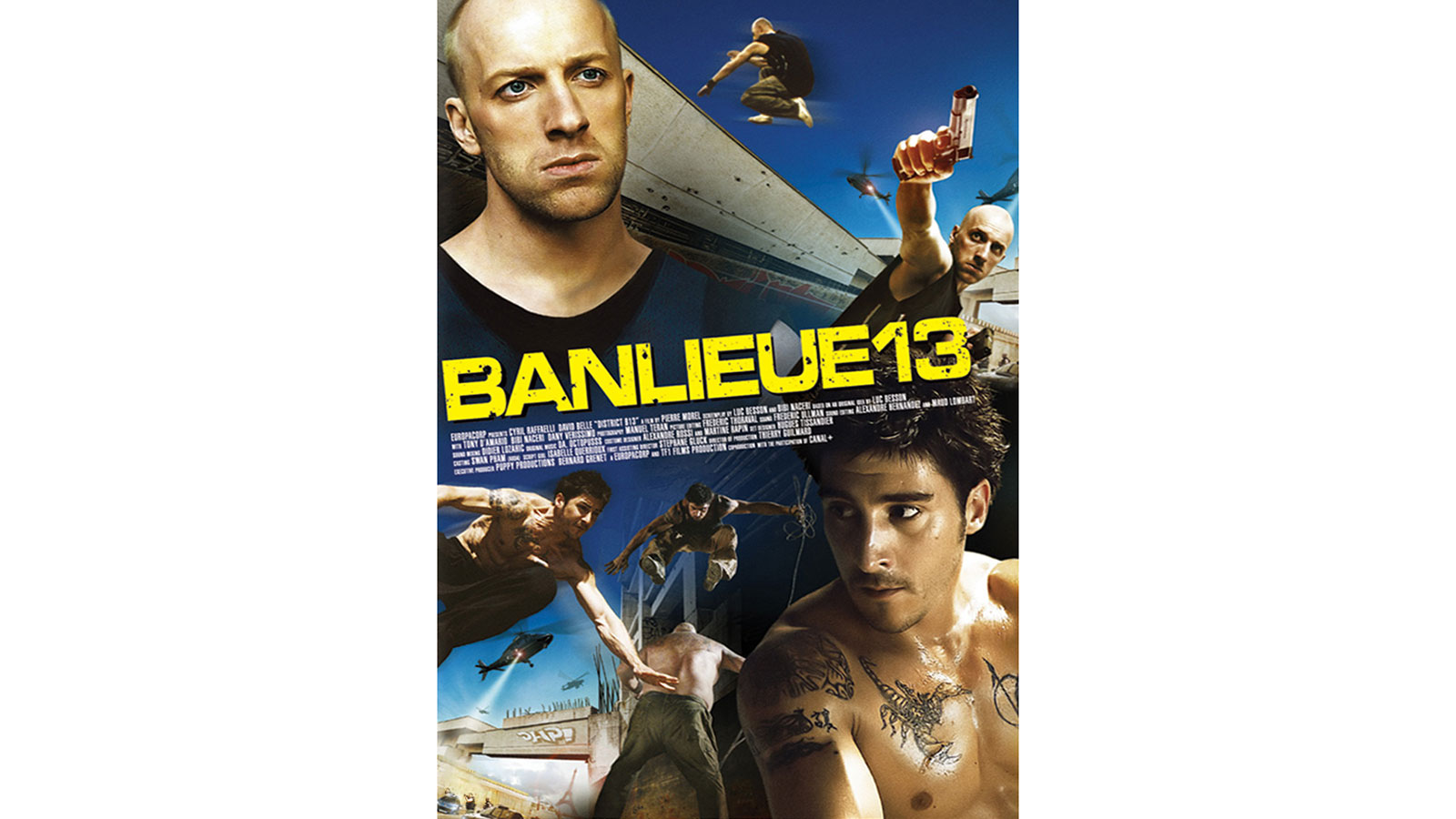
『アルティメット(原題:BANLIEUE 13)』製作・脚本:リュック・ベッソン 監督:ピエール・モレル/2004年公開、フランス。好評配信中 © 2004 EUROPACORP-TF1 FILMS PRODUCTION(Amazon Prime ※HDレンタル400円/U-NEXT)
――そういえば、たしかにハリウッドの大作でもパルクールっぽい動きはよく目にしますね。『007』なら『カジノ・ロワイヤル』(2006年公開)、『ワイルド・スピード』なら『MEGA MAX』(2011年公開)のチェイスシーンとか。
佐藤:まさにその『007/カジノ・ロワイヤル』の冒頭で、ジェームズ・ボンドに追われる男の役を演じているのがセバスチャン・フォーカンなんですよ。『TAXi②』『YAMAKASI』『アルティメット』の延長線上に、セバスチャンの『007』出演があったと思います。
「Casino Royale Movie CLIP – Parkour Chase (2006) HD」/『007/カジノ・ロワイヤル』冒頭で、ダニエル・クレイグ演じるジェームズ・ボンドが、謎の男を追跡するシーンの公式切り抜き動画。上記のYouTubeだけで2700万回再生されている。
――えええ!(笑)なるほど、そういう流れだったんですね。
パルクールの創始者「ヤマカシ」のルーツとは?
――ヤマカシがもともといて、フックアップしたリュック・ベッソンがいて…ということでカルチャーが生まれていったのだと思いますが、となるとヤマカシがパルクールを始めたルーツも気になります。
佐藤:これは話すと長くなるんですけど(笑)、「じゃあヤマカシが誰に憧れていたか?」っていうと、フィクションの中のキャラクターや映画スター以外では、メンバーの一人であるダヴィッド・ベルのお父さんのレイモン・ベルという人がその対象だったんですよ。
――『HUNTER × HUNTER』で言えば主人公ゴンのお父さんのジンみたいな人がいるわけですね。
佐藤:そうですね(笑)。そのレイモン・ベルは、子どもの頃にベトナムにあったフランス軍のキャンプで過ごしたんです。
――えええ(笑)! 子どもがなぜ軍のキャンプに…!?
佐藤:レイモンの父(=ダヴィッドの祖父)は第二次大戦の時期、当時フランスの植民地だったベトナムで働いていて、レイモンもその頃にベトナムで生まれています。しかし戦後すぐに起こった第一次インドシナ戦争でお父さんが命を落としてしまい、レイモンは軍隊の孤児院に預けられました。レイモンはそこで生き延びるために「メソッド・ナチュラレ(Méthode naturelle)」「パルコース・デ・コンバタント(parcours du combattant)」という障害物通過訓練のトレーニングを学んだんです。
――超ハードな状況じゃないですか…。そのトレーニングってどういうものなんですか?
佐藤:今の日本の自衛隊でもやっている、いろんな障害物を通過していく中でカラダをファンクショナルに鍛えていく訓練法ですね。レイモンはその後フランスに帰国して消防士として活躍し、鍛え上げられた運動能力によって数々の伝説的な救出劇の立役者となりました。そして子どものダヴィッドに自分の体得したトレーニングを教え、それを受け継いだダヴィッドがヤマカシの仲間たちと一緒にパルクールのかたちへと落とし込んでいったんです。
――めちゃめちゃ少年漫画的なアツいエピソード!
佐藤:大まかにまとめると『ドラゴンボール』、ジャッキー・チェン、レイモン・ベル。この3者をはじめとする憧れの人たちの要素を組み合わせ、ヤマカシたちにより形作られたパルクールが、リュック・ベッソンにフックアップされて世界中に広まっていった、という流れですね。
脚光浴びる中でのヤマカシの解散…中心地はフランスからロンドンへ
――『TAXi②』や『YAMAKASI』が公開されたのが2000年代初めですよね。そこからパルクール自体はどう発展していったのでしょう?
佐藤:実はヤマカシは、『TAXi②』や『YAMAKASI』が公開された2001年前後に、実質的に解散してしまうんですよ。
――それってインディーズバンドがメジャーになっていくときによく起こる「音楽性の違い」みたいな感じですか?
佐藤:そうですね。その頃にはすでに、ダヴィッド・ベル、セバスチャン・フォーカンと、他のヤマカシのメンバーのあいだで方向性の違いが生まれていたんです。そんな時期にダヴィッドがこの運動を、もともとの「パルクール・デュ・コンバタント(parcours du combattant)」から取り、少し綴りを変えて「パルクール(parkour)」と呼び始めたんです。
――でも、ここで遂に名前がついたんですね!
佐藤:はい。ただ、すぐにこの名前が、広く使われるようになったわけではないですね。その後パルクールが発展していく大きなきっかけとなったのが、イギリスのテレビ局が2003年に制作した『ジャンプ・ロンドン』というドキュメンタリーでした。これはパルクールをテーマにした作品で、セバスチャン・フォーカンがメインで出演しているんですよ。
――あれ!? “ロンドン”なんですね? フランスではなく?
佐藤:そうなんです。そもそも、この時期にパルクールの中心がフランスからイギリスへ移っていったんですね。
しかも、『ジャンプ・ロンドン』の撮影をしているときに、フランス語である「パルクール」が英語圏の人にわかりづらいからということで「フリーランニング」という新しい言葉が生み出されました。
――ほうほう、「フリーランニング」ですか。あんまり耳馴染みがないのですが。
佐藤:そこがひとつ重要なポイントだと思うんです。「パルクール」も「フリーランニング」も基本的には同じものなんですが、「フリーランニング」になったときに少し意味合いが変わったんですよ。
――おおー。それも気になりますね。では次回はフランスからイギリスへ、そして世界へという流れをもう少し詳しく伺っていきたいと思います。佐藤さん、引き続きよろしくお願いします!